成人式と会社説明会が合体!?
平成20年1月7日(月)付の愛媛新聞に、長野県小諸市で、地元の企業が地盤産業を知ってもらうとともに若者の人材確保のために「会社説明会」と「成人式」をセットで行うというユニークな記事が掲載されていました。
例年、「荒れた成人式」といわれて全国各地で新成人の荒れた行動が指摘されている昨今、行政担当者としても成人式のあり方については頭を悩ませているところが多いと思いますが、よくよく考えてみると「成人式」というのは黙っていても若い人があつまる一年に一回の行事ですから、そんな若い人が確実に集まる場をPRに使わない手はないということでしょうか。
しかも、主催者側にしてみたら、企業から「協賛金」という名のブース料もとれて成人式の経費も大幅に削減できるというのですから、行政コスト的にも大助かりです。
また、新成人の側からしてみても、「地元で働きたいけど、働き口がない」と諦めている若者に対して、地元企業、地場産業のことを知ることがきっかけができますし、場合によれば若い人の雇用につながる可能性もあります。
成人式が荒れてきたということで、松山市のように地域密着ということで大きなホールではなくて小学校区や中学校校区単位での同窓会形式の成人式を行うところが増えてきているようですが、小諸市の場合は新成人が400人ほどということもあり、新成人を出身の小中学校区ごとにテーブルにわけての立食パーティーの同窓会形式にし、それに加えて企業や地場産業のPRをするブースも設置して、その引き換えに企業から協賛金をもらって経費を賄うというスタイルを採用しています。
松山市くらいの50万都市で大学も複数あるようなところだと、「成人式+会社説明会」という形を実施してもなんとなくうまくいきそうなイメージももつことができますが、どうして人口わずか45000人の地方の小都市である小諸市で実施できたのかといえば、それは小諸市の有効求人倍率が1.15(平成19年11月末現在)と雇用情勢の良好な地域であり、若者を雇用する場が現実にあるということも要因のひとつとしてあげられるかもしれません。
ということは、愛媛県でも雇用情勢が比較的良好な東予地方であれば、「会社説明会」をセットにして実施するという「成人式」のスタイルはけっこううまくいくのではないか、と浅はかながら思ったわけなんですが、みなさんどうお考えですか?
(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)
年の暮れに夕日寄席を開催
またもや年末の話題で恐縮です。昨年の御用納め(12月28日)の終了後、若松進一さんが当センター職員に対して「夕日寄席」を行ってくださいました。
この夕日寄席とは、若松進一さんが11月に開催されました観光カリスマ塾(詳しくは研究員ブログを参照してください)で行ったもので、地域づくりに関する話題を小噺にして落語のようにお話しする講演会の形式で、そのお題についても配付された「夕やけ徒然草」という高座本の中から、聞き手側がリクエストできるという仕組みになっています。
今回の夕日寄席では、時間の都合により「お題をお客からのリクエスト」という形の寄席ではなく、若松さん、いやいや「夕日亭大根心師匠」自身が数あるお題のうち、「ハーモニカが吹けた」「外から見ないと中は見えない」「四つの願望」の3つを選んでお話していただくという形になりました。

最初のお題である「ハーモニカが吹けた」では、子どもの頃から音楽が苦手だった自分が、今では150以上もの楽曲をハーモニカで吹けるようになったことを通して、「努力することの大切さ」を教えていただきました。
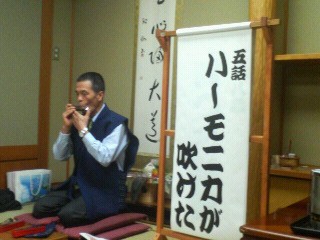
※ハーモニカも御披露いただきました。
次のお題の「外から見ないと中は見えない」では、学校の校庭などによく設置されている「二宮金次郎(尊徳)の像」が持っている本には何と書かれているのかというエピソードから、中にいるとなかなか分からないことも、外から教えてもらって分かることは多いということを教えていただきました。そして、その教えてもらったことを謙虚に受け止めて、それをどう生かしていくかも大事であることを教えていただきました。
ちなみに、この二宮金次郎の像が持っている本には、中国の古書である「大学」の一節が刻まれています。
最後のお題の「四つの願望」では、人間には「幸せになりたい」「お金持ちになりたい」「健康で長生きがしたい」「成功したい」という4つの願望があり、そういった願望をかなえた人たちは日々のコツコツした努力が実を結んでいるという事実をもっと知らなければならないといったことを教えていただきました。

※途中、指元に美男美女にしかとまらないというトンボが止まった「とっても男前」の方もいらっしゃいました(詳しくは若松さんのブログ参照)。
なお、この日、夕日寄席を聞きにきたのは当センター職員のほか、夕日寄席をぜひ聞きたいという県庁の市町振興課や企画調整課の職員有志の方なども集まり、総勢でおよそ20名ほどで夕日寄席を鑑賞しました。

ちなみに、この夕日寄席の様子については、若松さんのブログにも詳しく掲載されていますのであわせてご覧ください。
(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)
案山子庵を訪問しました
新春にもかかわらず、年末の話題を持ち出しましてたいへん恐縮です。
年末に、まちづくり活動部門の松本、坂本、谷本(通称:三本の矢)の3名の研究員が、西予市宇和町にある「案山子庵(かかしあん)」で行われました忘年会に招待されました。

※訪問する前に「わらぐろ」のライトアップを拝見しました。
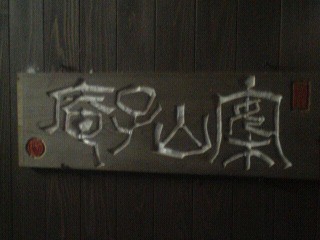
※案山子庵の看板
この「案山子庵」とは、えひめ地域づくり研究会議の事務局長をされている岡崎直司さんの私邸にある蔵を改装した別邸で、いわゆる「古民家」を改装したものです。

※忘年会の様子(この写真にはうつっていませんが、当センターの客員研究員である河井さん(現:大洲市役所)も、この忘年会に招待されました。

※上甲会長が作られた亀のしめ縄飾り。名人級です!
忘年会では、宇和のわらぐろの会の上甲会長さんや新聞社の記者さんも同席し、岡崎さんがつくったお米や上甲会長さんのご親戚がつくられたお豆腐など、地産地消の食べ物を頂戴したうえに、上甲さんがつくられた「注連縄飾り」や「わらぐろ」の話など、「地域づくり話」にたいへん花を咲かせた会となりました。
今回、はじめて「案山子庵」を訪問したのですが、古民家のあたたかさに包まれる生活というのはどこか落ち着くなあと思った次第で、いわゆる「移住」をする際に「古民家」にあこがれるというのがなんとなくわかったような気がしました。
なお、古民家といえば、何と言っても「南予の古民家再生プロジェクト」ですね。宇和町の中町には「よんでんなごみ館」という四国電力さんがつくった古民家再生プロジェクトのモデルルームがあります。古民家に興味のある方に限らず、田舎暮らしを考えている方、ぜひご覧になってみてはどうでしょうか。
(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)
センターからのお知らせ
○「財団法人えひめ地域政策研究センター」からのお知らせ
あけましておめでとうございます。
いつも「研究員ブログ」をご覧いただき、ありがとうございます。
さて、最近、「研究員ブログでイベントやセミナーの告知をさせてほしい」という依頼をよせていただくことがあります。
もちろん、そういう「告知依頼」は大歓迎ですのでどしどし当センターの研究員までメールをお寄せください。
ただし、記事として掲載するのは、「地域政策」や「まちづくり」に関する内容と判断させていただいたものに限りますので、あらかじめ御了承ください。
また、本日、調査研究情報誌「ECPR」22号と「舞たうん」95号の発送作業を行いました。会員の皆様、関係者の皆様におかれましては、読んだ感想や御意見などがありましたら何なりとセンターまで御連絡ください。また、それぞれの雑誌の見所などは後日の「研究員ブログ」で担当編集者が御紹介いたします。
ちなみに、今日の「研究員ブログ」はこれでおしまいです。来週から気持ちもあらたに気合を入れて「研究員ブログ」も投稿していきますので、御期待くださいませ。 決して正月気分が抜け切れていないわけではないのであしからず(笑)
(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)


