2007なんよ地域づくり事例発表会
平成19年9月6日、西予市の愛媛県歴史文化博物館で「2007なんよ地域づくり事例発表会」(第26回政策研究セミナー)が行われました。今回は愛媛県と当センターが主催、愛媛大学が共催で開催されました。当日は行政やまちづくり関係者など約200名にご来場いただき、会場となった多目的ホールはほぼ満席となりました。
はじめに県外先進地での取り組み事例の紹介として島根県江津市のNPO法人結まーるプラス理事長かわべまゆみ氏に、「無人駅が観光・定住・ITのサービス拠点に」と題して講演していただきました。島根県江津市へIターンした経緯やインターネットを利用した地場産品販売の秘訣などマーケティンのプロならではの貴重なお話を聞くことができました。
その後、愛媛大学の有馬准教授から(財)えひめ産業振興財団や愛媛大学、井関農機などが連携して取り組んでいる「植物工場の現状」についての説明や他地域の植物工場の事例紹介がありました。
そして休憩をはさみ「これからの南予の地域づくりについて」をテーマに地域づくり実践者によるパネルディスカッションが行われました。パネリストは八幡浜ちゃんぽんプロジェクトの仕掛人である八幡浜商工会議所青年部前会長の伊藤篤司氏と宇和島市の岩松地区でどぶろくの製造などで町づくりに取り組んでいる宇和島市役所津島支所の森田浩二氏に結まーるプラスのかわべ氏が加わり3名で行われました。八幡浜ちゃんぽんプロジェクトとどぶろく製造の取り組みについての苦労話や今後の展開などについて説明があり、最後に今後の南予地域活性化にむけての地域資源活用のポイントやネックなどについて意見交換が行われました。
印象に残ったのはかわべ氏がIターンされた時の話でした。かわべ氏は、東京でマーケティングの仕事をしながら都会での生活を送っていましたが、夫の希望もあり夫の里にIターンされました。ただその時にはかわべ氏自身は田舎暮らしに何の興味もなかったとのことでした。ただ地方都市で生まれ、大都会の生活も経験したので、あと経験していないのは田舎の生活だけだから、それを経験できる良いチャンスだと考えたとのことでした。
この発想の転換というか前向きの姿勢というか思い切りの良さは、なかなか真似ができないことだと思います。講演からは、かわべ氏のパワフルなオーラとプロ意識の高さが伝わってきました。
もう一つ印象に残ったのは、マーティングの大切さです。同じ商品でもパッケージなどの見せ方次第で売れ行きが変わります。もちろん品質は大事ですが、良い商品を作りさえすれば売れるというものではありません。買う側がその商品を見て何を感じるかが重要です。これは売れないと思っても違う感性で見ると魅力的な商品になります。
たとえば“一番”とか“大和魂”とか書かれた日本語のTシャツを私は買いませんが、外国人は日本のお土産として買っていくというようなことです。地域資源を地域ブランドとして売っていくためには、熱い思いだけではなくクールな感性と分析力も必要だと思いました。
(文責 企画研究部門 研究員 河野 洋)
調査研究情報誌 ECPR21号 「地域産業の再生~内発型ビジネスへの期待~」
調査研究情報誌 ECPR 21号 を、8月31日に発行しました。特集は「地域産業の再生~内発型ビジネスへの期待~」です。
地域活性化のためには、地域を支える産業の再生が不可欠ですが、経済のグローバル化とIT化の進展のため、地域産業はこれまで拠り所としてきた安価な用地や労働力などのアドバンテージを失い、そこに立地集積する意味自体が薄れてきています。
今回の特集は、域外企業の誘致に頼るだけでなく、埋もれた地域資源を見出し、新たな付加価値を創造して事業化するプロセスを各地域で自発的に行う、いわゆる内発型ビジネスの創出による地域産業再生の取り組みについて取り上げました。
地域イノベーションと地域の再生、産業別開業率にみる地域間格差とその要因、徳島県、松山市、岩手県花巻市における地域活性化への取り組み等について掲載しています。
詳しくは、本ホームページの「事業のご案内」-「調査研究情報誌ECPR」をご覧ください。ご参考になれば幸いです。
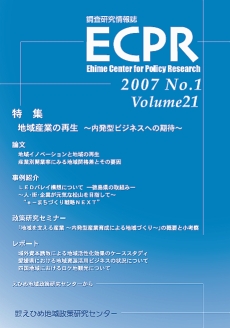
(文責:企画研究部門 研究員 政木輝彦)
愛媛ふるさと暮らし応援センター、いよいよ開所!
本日、おもに団塊の世代の方を対象にした愛媛県への移住を支援のための「愛媛ふるさと暮らし応援センター」が、(財)えひめ地域政策研究センター内に開所いたしました。
※看板設置の様子(栗田所長が看板設置)
午前10時30分からの開所式では、応援センターの看板を入り口に掲示して、愛媛ふるさと暮らし応援センターの専従職員2名体制による移住支援業務がスタートいたしました。
そして、応援センター長を兼ねる栗田史朗(財)えひめ地域政策研究センター所長が開所にあたり、「この応援センターが団塊の世代の方をはじめ、多くの移住希望者の拠り所となるようにがんばっていきましょう」とあいさつをいたしました。
これまで、「えひめ地域政策研究センター」でも「UJIターンに関する情報提供」をホームページ内で行ってまいりましたが、この「愛媛ふるさと暮らし応援センター」が開所したことにともない、これまで「えひめ地域政策研究センター」のもっていたUJIターン情報を継承した愛媛の移住ポータルサイト「e移住ネット」も本日から開設されました。
このポータルサイトでは、愛媛県の移住支援につながる情報を総合的に網羅・提供していきながら、住まい、仕事、暮らしに関する各種の情報提供を通じて愛媛の移住に関するホットな情報とともに、サイト内にある案内人のブログ「えひめ移住案内人レポート」では愛媛県への移住体験者などの生の声をどんどんお伝えしていく予定です。
愛媛に移住をお考えのみなさん、ぜひポータルサイトをご活用の上、「愛媛ふるさと暮らし応援センター」にお問い合わせください。そして、愛媛県への移住を職員一同心よりお待ち申し上げております。
なお、この研究員ブログでも移住・交流に関する情報を投稿する場合がありますので、あわせてご覧ください。
愛媛ふるさと暮らし応援センター
TEL:089-932-7841(担当:坂本、濱田)
愛媛県への移住ポータルサイト「e移住ネット」アドレス
http://e-iju.net/
(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)
第26回地域づくり団体全国研修交流会愛媛大会実行委員会設立
9月4日(火)、西予市中央公民館において、第26回地域づくり団体全国研修交流会愛媛大会実行委員会の設立総会が開催されました。
この「地域づくり団体全国研修交流会(以下、全国大会)」は、全国の地域づくり活動に携わる関係者が一堂に会して研修や交流を図ることを目的に毎年1回開催されており、平成20年度に愛媛県で開催することが内定しています。
この全国大会は、開催県において実行委員会を組織して実施していますが、この大会のメインとなる分科会の開催にあたっては、地域づくり団体が地元市町のサポートを得ながら企画・運営する形態になっており、愛媛県ではこの大会の開催を「南予活性化策のひとつ」として位置づけて、平成18年度より関係市町のまちづくり担当課の皆様と検討・協議をすすめてまいりました。
また、この全国大会は、全体会の中で、次期開催県があいさつとともにPRを行うのが通例となっており、本県も19年度の茨城大会において、次期開催県のPRを行うことになっています。
そこで、 茨城大会においてより効果的なPRを図り、また愛媛大会を実りある大会にするために、開催前年度である今年度から実行委員会を設立し、愛媛大会に向けて具体的な準備をすすめていくこととなり、9月4日に設立総会を開催する運びとなりました。
今回、実行委員として参画していただいたのは、南予を中心とした県内15の地域づくり団体の代表者のみなさんと、その団体所在地の市町まちづくり担当課の職員のみなさん、その他の関係者のみなさんの合計34名で、設立総会のこの日には32名の実行委員の方々にご出席いただきました。
※実行委員会の様子
実行委員会では、まず実行委員会の規約(案)が承認された後、規約に基づいて役員が選任され、実行委員長には「えひめ地域づくり研究会議代表運営委員」の若松進一さんが選任されました。
※実行委員長の若松さん
その後、実行委員長の司会のもと、事務局である当センターから実行委員会の事業計画(案)、予算(案)が提出され、それぞれ審議の後原案の通り承認され、今後の実行委員会の開催スケジュール等を確認しました。
なお、実行委員会事務局では、愛媛大会に関する情報については「実行委員会NEWS」というページを新たに当センターのHP内に開設し、実行委員会の会議の様子のほか、分科会を運営する団体のみなさんに関する情報や準備作業の様子などを発信していき、少しずつ愛媛大会を盛り上げていく予定ですので、そちらもあわせてぜひご覧ください(実行委員会NEWSのページは9月10日に公開予定です)。
また、この実行委員会の様子は9月6日付の愛媛新聞に紹介されるとともに、若松進一さんのブログでも記事紹介されていますのであわせてご覧ください。
(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)
第25回政策研究セミナーを開催しました
平成19年8月23日に第25回政策研究セミナーを開催しました。当日は大勢の皆様にご来場いただき、大変盛況な講演会となりました。
今回は、コミュニティ・ビジネスの伝道師であられる(有)コミュニティビジネス総合研究所 の細内信孝所長をお迎えして、「地域資源からビジネスへ~コミュニティ・ビジネスの可能性~」をテーマにお話をいただきました。私自身、「コミュニティ・ビジネス」という言葉を、本年4月に当センターに派遣されてから知りましたが、講師のお話や著書等に触れる中で、コミュニティ・ビジネスは、現在の社会情勢における地域活性化策として非常に有効なツールであるという印象を受けました。
また、今回のセミナーと合わせ、愛媛県研修所が主催された地域課題解決講座(~コミュニティ・ビジネスの手法を学ぶ~)にも参加し、実際に事業企画書や店舗(事務所)の計画書、資金計画書などを作成し、研修の最後には各班ごとにビジネスプランを発表するなど、実践的な内容について学習させていただきました。ある程度の予備知識を持って臨んだ研修でもあり、事業企画書や店舗などの計画書作成までは何とか進めたものの、資金計画書の作成段階で頓挫してしまい、起業の難しさと自分のビジネス感覚の無さを痛感いたしました。細内講師も、コミュニティ・ビジネスはある程度継続した活動でないと成果が出ないとお話されたように、ビジネスの視点における資金計画は重要なポイントであり、この部分が曖昧だとコミュニティ・ビジネスとして成立しないということです。
ちなみに、私の所属した班のビジネスプランは、上島町を舞台にした島の便利屋さん業、名付けて「かけはしサービス」(上島四島にコミュニティの橋を架けるという意味ですが・・・)を提案いたしました。内容を簡単にご説明しますと、島内の企業などの退職者で構成するNPO法人を立ち上げ、庭の草引き、買い物の代行、家具等の組み立て、雨戸の修理、レモンの収穫など、島内の身近な課題やニーズを住民から請け負うという事業でしたが、資金の調達方法など、資金計画の甘さをご指摘いただき、改めてビジネスの難しさと、マネジメント能力を有する人材の必要性を感じました。なお、 コミュニティ・ビジネスや講師についての詳細はこちらまで。
さて、次回の政策研究セミナーは、平成19年9月6日(明後日ですが・・・)NPO法人結まーるプラス理事長のかわべまゆみ氏をお迎えし、「2007なんよ地域づくり事例発表会」を開催します。地域づくり先進地での取り組み事例報告や、地域づくり実践者によるパネルディスカッションなどを予定しております。詳細並びにお申し込みはこちらまで。
(文責 企画研究部門 研究員 渡邊赴仁)


