地域づくり団体全国研修交流会
昨年度愛媛県で開催した地域づくり団体全国研修交流会が、今年度は佐賀県で開催されましたので、県内の関係者37名で参加してきました。
「もやい」でつなぐ「協働のまち」~平成まちづくり維新は佐賀から~をテーマに、前夜祭、全体会、13の分科会と内容の濃い研修となりました。佐賀大会も前年度に実行委員会組織を立ち上げ、事務局機能をNPO法人佐賀県CSO推進機構が務められました。
佐賀県では、NPO法人、市民活動・ボランティア団体に限らず、自治会、町内会、婦人会、老人会、PTAといった組織・団体を含めて、Civil Society Organizations(市民社会組織)の略で「CSO」と呼称しているそうで、13の分科会もそれぞれの自治体にあるCSOの組織が運営に当たっていました。
私は、第9分科会(鹿島市)に参加し、豊かな海・山・里の歴史文化を体験してきました。特に運営主体であった「フォーラム鹿島」が目指す『プロ市民』という言葉に共感を持ちました。行政や補助金に頼るばかりではなく、まず「自分自身が、ふるさと鹿島のまちづくりのために何ができるか考え、具体的に行動する」という考え方が鹿島の地域力を上げていると確信しました。
地域づくり団体全国協議会に登録する団体は、年々増えていますが、こうした全国の地域づくり人が集まる研修会に参加することで、改めて自分のやらなければならないことを痛感する次第です。来年度は、11月に青森県で開催されることが決まっています。今から毎月積立して参加しようと思っています。
(潟スキーの実演をしてくれた鹿島市の職員さん)
(まちづくり活動部門 研究員 松本 宏)
トークサロン
2/19(金)13時30分から愛媛県美術館講堂で「トークサロン」を開催します。
今回の基調講演は、テレビでも話題となりました「四万十川新聞バッグ」などを制作・販売し、自然循環型企業として「『四万十川方式』地元発着型産業づくり」に取り組まれている株式会社四万十ドラマの畦地履正氏です。
また、パネルトークは、「地域資源を活かした販売戦略」と題して、実践者とともに考えるサロンとなっています。
パネリストは、「みかめ海の駅潮彩館」の山城辰紀さん、「ぎんこい市場」の向井京子さんと畦地履正さん。コーディネーターは、愛媛大学社会連携推進機構の村田武教授で、実践に基づいたトークを予定しています。
なお、サロン終了後に、実践者とともに語れる交流会も予定していますので、ぜひ、ご参加ください。詳細は、ホームページで。
(まちづくり活動部門 研究員 武田 昭文)
高知県における温室効果ガスの排出
1月28日(木)の日本経済新聞において、高知県の2007年度における温室効果ガス排出量が1990年度対比で5.2%削減されたことが掲載されていた。産業部門、民生部門は増加したが、農業・廃棄物部門が減少したのに加え、間伐による森林吸収量の増加が寄与したそうである。1月6日(水)に同じ日本経済新聞において、愛媛県の2007年度における温室効果ガス排出量が掲載されていたが、13%増加となっていた。高知県では、オフセット・クレジット(J-Ver)の導入を実施し、地球温暖化防止に積極的に取り組んでいます。愛媛県においても、多くの森林が賦存していることから、オフセット・クレジット等の利用により、地球温暖化防止先進地となるべく、その取組みの実施を期待しています。
(企画研究部門 研究員 三好進祐)
鯨文化
先日、反捕鯨団体「シー・シェパード」の妨害船「アディ・ギル号」が南極海で日本の調査船と衝突し沈没した事故がありました。調査捕鯨というものは世界的に認められた行為であり、国際法上何ら問題はない行為ですが、要は日本と欧米の価値観、文化の違いによって起こる摩擦であるといえます。
少し前までは、欧米でも捕鯨は一般的でした。主に鯨の油を原材料として使うためです。このことは過去に何度も映画化され、世界でも題名を知らない人はいないだろうと思われる有名な小説『白鯨』を読めば分かります。ただ、鯨を食べるという文化は世界でも稀ではあるでしょう。日本にとって鯨は文化史や産業において「動物」ではなく「魚」であり、この文化には日本人特有の畏怖や感謝の念があらわれている事柄があります。
日本全国各地には、昔から鯨を供養するための神社やお寺、鯨のお墓や碑などが数多く存在し、(イルカもある)愛媛県でも伊予市や西予市、宇和島市、伊方町、瀬戸町、愛南町などに存在します。そのほとんどは鯨に対する追悼や感謝の念からで、飢饉に苦しんでいた村に鯨が打ち上げられ飢えをしのぐことができたため、感謝の気持ちから建てられた話や、母と子の鯨を捕獲した際に母鯨の死骸に子鯨が母乳を飲むような姿で離れようとせず、結局子鯨まで死なせてしまい、その様を見て食べるに忍びずお墓を建てて供養した話などがあります。
ある話で、欧米で反捕鯨活動をしていた女性が訪日して鯨を祭る神社を訪れ、感極まって涙したことがあるそうです。反捕鯨国家のどこにも、これほど鯨を大切にする文化は無かった、と。彼女は後に、文化由来の捕鯨は認めるべきと立場を変えたとのことです。
お互いの価値観、文化を理解することも必要なのではないかと思います。
(企画研究部門 研究員 向井浩司)
カーボンフットプリント
2月1日より、カーボンフットプリントマークを貼付した製品が、全国の店頭で販売されることとなりました。
カーボンフットプリントとは、低炭素社会実現への取り組みの一環として、製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るライフサイクル全体において排出される温室効果ガスをCO2量に換算しわかりやすく表示するもので、経済産業省等が、本年度より試行的に実施しており、温室効果ガス排出量の「見える化」によってその削減を進めていこうという取り組みです。
今回、第一号として2月1日より店頭販売される製品は、ウインナー及びロースハムの一部で、これらの製品については、カーボンフットプリントの算定結果及び表示方法に関して検証が行われ、その内容が適正と判断されたため、次のようなカーボンフットプリントマークを貼付した上で製品を販売することが認められたものです。

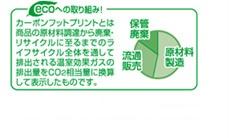
このマークの製品の場合、ライフサイクル全体でCO2量に換算して638gの温室効果ガスを排出していることになります。先行して実施しているイギリス、フランス等では文字通り「フットプリント(足跡)」のマークだったようですが、日本では、「食品に足で踏んだ跡?」ということでこのようなマークになったようです。
低炭素社会では、原産地、原材料の表示と同じくらい、広まっていくのかも知れません。
(企画研究部門 政木輝彦)


