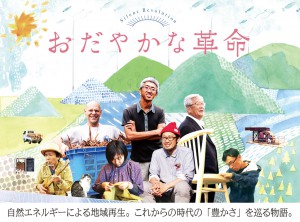令和リレーブログ その35
お久しぶりです。研究員の徳永です。
2月も半ばとなり、春が待ち遠しい時期になりましたね。
私は季節の変わり目に必ず風邪をひいてしまうのですが…、みなさまはお元気でお過ごしでしょうか?
今年は全国的にも暖冬で、例年に比べると暖かい日が多いですが、それでも朝晩は冷えますので、体調にはお気をつけください。
さて、建国記念日の2月11日、ピュアフル松山勤労会館で行われた「田園回帰1%戦略 成果報告会」に参加してきました。
愛媛県では、松野町蕨生・奥野川地区、愛南町緑地区、伊予市三秋地区の3地区をモデル地区として、「集落活性化モデル構築事業」を始めて2年が経とうとしています。今回は各地区代表者の方々より成果報告が行われました。
この会のタイトルにもなっている「田園回帰1%戦略」とは、平均すれば毎年人口の1%程度、つまり住民100人につき1人の定住増加を実現すれば、概ね地域人口が長期的に安定するという理論です。今回はこの理論を提唱されている、(一社)持続可能な地域社会総合研究所の所長 藤山 浩先生にお越しいただき、基調講演「定住と循環実現に向けた地元の進化戦略」をしていただきました。
藤山先生は、2月27日に宇和島市で行われる「持続可能な地域構造シンポジウム~地方都市圏の現実と未来~」(主催:国土交通省)で再び来県され、講演されます。先着順の事前申込制とのことですので、ご興味のある方はお早めにお申し込みください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、開催中止となったとのことです。
↓詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。↓
https://www.mlit.go.jp/report/press/kokudoseisaku09_hh_000099.html
ところで、ここ数日の間、昼休みに装飾用のペーパークラフトを作成中なのですが…私の手先の器用さでは、先は長そうです(汗)
今週末の移住フェア「愛あるえひめ暮らしフェアin大阪」(2/15(土)13:00~18:00 ディアルーム大阪にて開催)には、みきゃん(本物)も駆けつけてくれるそうなので、お知り合いの方で移住に興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひお声がけください。
今年度最後の大阪フェアです!詳しい内容は、e移住ネット(https://e-iju.net/)をご覧ください。今後のフェア開催予定も、決まり次第こちらでご案内していきます。
ちなみにこのペーパークラフトは、愛媛県庁のホームページ(https://www.pref.ehime.jp/h12200/mican-kanzume/download.html)からダウンロードできますので、みなさんもぜひ!
それでは、またお会いしましょう。
PS.次回は宮本研究員にリレーします。
令和リレーブログ その34
研究員の越智です。立春になりましたが、まだまだ寒い日が多いようですので、風邪等には十分お気をつけ下さい。
さて、今回は2月2日(日)に東京都千代田区有楽町にある東京交通会館で開催された「愛媛・愛南町みどり 海・山・農のある暮らしセミナー」をご紹介します。
本セミナーは、愛媛県地域政策課からの受託事業である「集落活性化モデル構築事業」のモデル地区の一つとして選定している愛南町緑地域の「まるごと緑」が主催し、えひめ地域政策研究センター等が共催したものです。当日は、田舎暮らしにご興味を持たれている関東圏在住の10数名の方にご来場いただき、愛南町の自然豊かな暮らしなどについて幅広く学んでいただきました。
まず初めに、愛南町のプロフィール動画を皆さんにご覧いただいた後、まるごと緑の代表である木村俊介氏と愛南町地域おこし協力隊の森裕之氏から、愛南町及び緑地域の魅力などについて熱く語っていただきました。また、森氏が地域おこし協力隊を卒業した後に、愛南町内で計画している地域おこしに関する具体的な事業についてもご紹介がありました。
一方で、愛南町の自然豊かなバラ色に満ちた田舎暮らしの生活をご紹介しただけでなく、「愛南町暮らしの損得」と題して、例えば自家用車を所有していないと生活しにくい点や、南海トラフ大地震発生時には大きな被害が想定されていることなど負の面についても紹介しました。
つづいて、愛南町の特産品についても知っていただく目的で、「なーしくんどら焼き」や特産のポンカンを食していただき、さらには愛南町産の柑橘ジュースである「甘夏」や「河内晩柑」も飲みながら、愛南町での暮らしについて語る「雑談会」も行いました。
その雑談会ではご来場された方に、本日参加された目的について尋ねてみました。来場者からは、「定年を機に移住を考えている」「田舎暮らしに憧れている」「自然豊かなところに移住したく、様々なセミナーに参加し情報収集している」など、移住について漠然と考えておられる方もいれば、「愛媛大学と連携し、自然とITとを融合した取組みに興味がある」「3×3ラボで行われている大丸有についての取組みに興味がある」「これまでに愛南町に3回行っているが本気で移住を検討している」など地域に対して具体的なイメージを持たれている方や、本気で移住を考えている方もおられました。
今回、田舎暮らしをPRするセミナーを東京で初めて開催しましたが、都会は人間関係が希薄で生きにくいと思っておられる方も多いようで、田舎暮らしに憧れを持っている方も少なからずおられることを知りました。
今後も、東京や大阪において、今回のようなセミナーを各市町とも協働して開催し、県内各地域の魅力を発信し続けていくことが大切であると感じました。
PS.次回は徳永研究員にリレーします。
令和リレーブログ その33
こんにちは。えひめ移住コンシェルジュの板垣です。
先日、移住イベント参加のため出張で東京に行った際、神奈川県鎌倉市にある面白法人カヤックに伺いました。カヤックはWeb制作・企画やイベントの企画などを行う会社ですがその名の通り面白いことをしよう!という理念で活動しています。
代表的なところだと、東京や横浜にある「うんこミュージアム」の企画制作であるとか、100人近い参加者がみんなでブレストする「カマコン」などを手掛けています。
そんなカヤックのグループ会社「カヤックliving」の担当者に移住マッチングサービス「SMOUT」についてのお話を伺いました。
SMOUTは、移住したい人(もしくは地域に興味がある人)と地域を結ぶマッチングサービス。全国の各市町村やその関連団体が独自プロジェクトを用意して掲載、そのプロジェクトに興味を持ったユーザーがプロジェクト提供者とコンタクトをとる、というものです。
例えば、「○○町地域おこし協力隊募集」というストレートな求人募集から、「〇〇村の魅力を紹介!」というような地域をPRする投稿まで様々です。ユーザーは、面白そうだなと思うプロジェクトに「いいね」ボタンを押したり、チャット形式でコミュニケーションを取れたりととても便利なサービスです。
なので、移住のマッチングといっても実際に移住者したい方をつなぐ、というよりは関わりを持ちたい方を地域とマッチングさせる、いわば関係人口を作り出すためのサービスといえます。
またカヤックでは、地域の特徴や強みを地域資本と定義しその指標を伸ばす取り組み「地域資本主義」という考え方を掲げています。このように拠点をおく鎌倉市の活性化にも力を入れています。先に紹介した「カマコン」なども、地域住民のみならず鎌倉に関係する人々みんなを巻き込んだイベントを開催し街を元気にしています。また、起業したい人と地域の人とのつながりをつくる起業支援拠点「HATSU」というコミュニティスペースを神奈川県からの委託事業として運営しています。起業家やベンチャー企業の創出も積極的に支援しています。
来年度の移住促進のツールとしてSMOUTのサービスはぜひ利用してみたいですし、鎌倉市での取り組みもぜひ参考にしたいと思います。
令和リレーブログ その32
研究員の上本(あげもと)です。2年間の出向生活もあと2か月ほどとなりました。今回は2年間の研究の集大成?として編集した舞たうん143号の編集後記として書かせていただきます。嬉しいことにお二人の方から直筆のお礼状をいただきました。
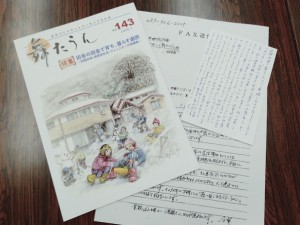
アングルでは、「田舎の田舎で育ち、暮らす選択」と題してこの2年間、愛媛県の受託事業でお世話になっている「持続可能な地域社会総合研究所」の藤山浩氏に新たな時代のうねりについて解説していただき、その実例として7つの特集を組みました。
特集①では、映画「おだやかな革命」の渡辺智史監督に地域内エネルギー循環について寄稿していただきました。実は映画館で映画を見るのは、仕事の関係で砥部町出身の大森研一監督が手掛けた「瀬戸内海賊物語」(2014)と「海すずめ」(2016)を観て以来で4年ぶりです。個人的に観に行ったのはブルースウィルスの「アルマゲドン」かレオナルドディカプリオの「タイタニック」が最後かも知れません。文化的素養が足りないですね。
特集②では、同じく県の受託事業でお世話になっている松野町の森の国まきステーション代表の谷清さんに寄稿していただきました。地域内エネルギー循環の先進事例は、宮崎県日之影町の小水力発電や、内子町小田の木質バイオマス発電などたくさんありますが、できるだけ小さなスケールで運営している事例として選びました。地域の高齢化に伴う事業拡大の難しさや、収支バランスの改善など問題は山積しているようですが、小さな町の大きな挑戦の応援としての意味も多分に含まれています。
特集③では、地域資源の住民レベルでの活用事例を取り上げようと、島根県雲南市の里山照らし隊の堀江智浩氏に寄稿を依頼しました。本当は、竹炭を使って蓄電池を開発・製造している事例をメインに考えていたのですが、事業がまだ軌道に乗っていないとのことでもう一つの事業である草刈り応援隊をメインに寄稿していただきました。交流人口の拡大ツールとして草刈りが活用できていることは、同じ環境にいる私としては驚きを隠せませんでした。繋がりの大切さや、メディアへの露出の大切さが実感できる好事例でした。
特集④では、田舎の田舎の多世代交流のツールとしての木育を取り上げようと、秋田県由利本荘市教育委員会の佐藤弘幸氏に寄稿していただきました。新宿の東京おもちゃ美術館でもなく、山口県の長門おもちゃ美術館でもなく、鳥海山木のおもちゃ美術館にしたのはたまたま(一財)地域活性化センター主催の第7回地方創生実践塾が開催されるタイミングだったのもありますが、田舎の田舎というテーマに一番合致した環境だったからです。野生のカモシカが美術館の周りを走っている豊かな自然環境にあり、国の登録有形文化財に指定されるほどの元小学校施設をリノベーションした美術館は見ておくべき価値のあるものでした。
特集⑤では、田舎の田舎で育つ観点から森のようちえんの事例を取り上げようと(一社)ノヤマカンパニーの加藤千晴氏に寄稿いただきました。森のようちえんは全国各地で取り組まれていますが制度として確立しているわけではないので運営者の思いが活動に如実に表れています。公的なシステムにもう少し組み込んでいい活動と考えていますが、活動のフレキシビリティを無くさない配慮が必要です。
特集⑥では我田引水的ではありますが、私が地元で所属する地域づくり団体「元気・ひろた」を考える会で精力的に活動してくれている立田卓也氏に移住者としての田園回帰の可能性について寄稿してもらいました。少子高齢化に疲弊する過疎地域は学校が廃校になるなど暗い情報ばかり発信されますが、実は日本の持続可能性を一番先に実現し、発信できる地域になれるポテンシャルがあると感じています。皆さんはいかがでしょうか。元気ひろたについては次の機会にご紹介させていただければと思います。
特集⑦は平成17年から20年度まで砥部町山村留学センターの運営スタッフをしていた時に、山村留学の理想形として注目していた暮らしの学校「だいだらぼっち」の辻英之氏に寄稿していただきました。辻氏への寄稿依頼は講義をしている池袋の立教大学でしたのですが、現地を見ないことにはと思い、長野県泰阜村の施設もスタッフの方に案内してもらいました。自立した自給自足に近い生活を送る小学生の成長は田舎の田舎でしか実現できないものだと確信しました。
それ以降のページについても書きたいところですが、長くなりましたのでこの辺りで終わりにします。冊子については弊社のホームページに公開していますので興味のある方はのぞいてみてください。
えひめ地域政策研究センターHP 刊行物のご案内
令和リレーブログ その31
研究員の玉井です。今年もよろしくお願いします。
みなさんお正月は、いかがされたでしょうか。
私は、食べて寝ての繰り返しで少し正月太りになりました。
そこで普段、私が散歩している松山総合公園をご紹介します。
この公園、山頂から見る景色が抜群で、360度の眺望が出来、松山平野
が全て見え、松山市の主要な場所、松山城、松山空港、興居島、中島、はたまた
伊予鉄高島屋のくるりん等最高のロケーションです。
特に夜景がきれいでヨーロッパ調の古城から見る展望台は最高です。
また他に山頂まで登る道の横は、季節ごとにいろいろな花が咲きとてもきれいです。
おまけに、足裏を刺激するロードもあります。
ぜひ皆様も山頂までトライして下さい。この絶景は絶対に見ておくべきです。
PS.次回は上本研究員にリレーします。