第28回政策研究セミナー
12月12日(金)、第28回政策研究セミナーが県立美術館講堂で開催されました。今回は富士宮やきそばを地域ブランドに確立した渡辺英彦氏(富士宮やきそば学会会長)をお招きし、「B級ご当地グルメで街おこし」という演題で講演していただきました。
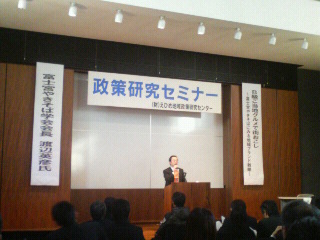
渡辺さんの軽妙な「おやじギャグ」と語り口により、会場からは笑いも飛び出すような和やかな雰囲気のもと、富士宮やきそばによるまちおこしの体験談から来る、地域ブランド確立に向けたお話を聞かせていただきました。
「ものづくり」から「ものがたり」へ。
地産地消など、全国各地でおいしいものはいっぱいありますが、それをまちおこしの道具として売り出す時には、大手企業のように広告宣伝にお金をかけることができるのであればいざ知らず、そういう宣伝費用がない中で、どうやってPRするかといえば、マスコミに取り上げてもらえれば、宣伝費用はタダです。となれば、マスコミが取り上げてもらいやすいようにしなければなりません。
味がおいしいのは前提として当たり前で、あらたなものでまちおこしをしようとしたら、マスコミも最初は物珍しがってとりあげてくれるかもしれませんが、継続してマスコミは取り上げてくれません。そこに物語やストーリー、いわば話題性がないと、取り上げてくれないわけです。
「ものづくり」の世界は専門家の世界であり、作る側の論理だけでは「もの」が売れないからです。同様に、まちづくりの世界も行政や商工会議所など専門化されてきており、既成概念にとらわれてしまいがちです。ですから、制約があります。
したがって、「もの」が売れるようにする、もしくは「まちおこし」に成功するためには、「ものを売るため」の、「町を売るため」のストーリーづくり、話題作りにシフトすべきで、そこには既成概念にとらわれない素人の発想が必要となるともおっしゃられていました。
もちろん「ものをつくる人」、「まちをつくる人」は必要ですが、それを「うまく売る人」という、コーディネーターともいうべき存在をもたなければ地域ブランドはつくれないということなのでしょう。この話は若松進一さんがお話しされる「夕日のまちづくり」と同じだなあと思って聞いておりました。
興味のある方、富士宮やきそばのまちおこしのすべてがわかる「YAKISOBIBLE(ヤキソバイブル)」と呼ばれる本もありますので、ご一読ください。
(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)
「島でcafe」がオープン!
上島町弓削島で地域づくり活動をがんばっておられる兼頭一司さんが、このほど地産地消にこだわったカフェをオープンさせました。
「島でcafe」と名付けられたこの店舗は、上島町役場のすぐ目と鼻の先にあった民家を改築・改装してできたお店で、地元で取れた野菜のサラダや地魚を使ったパスタ、はちみつカレーが主なメニューとなっており、メニューの中には地元のおばちゃんの名前が入っているものなどもありました。
兼頭さんのお店は、株式会社の形態をとり、住民有志による出資で資本金を集めて開設されており、いわゆる「コミュニティビジネス」の典型的な例と言えますが、もともと兼頭さんはJターン者で地元出身ではなく地縁も血縁もないにもかかわらず、地域に溶け込んで、出資者を集め、そして「島おとこ」として、地域づくり活動に奮闘されておられる兼頭さんの熱意には頭がさがるばかりです。
ただ、お店を開設して間もない時期ですから、今後は運営や経営面で困難な面がでてくるのではないかと思いますが(いらぬ心配だといわれるかもしれませんが)、ぜひともがんばっていただきたいと心からエールを送りたいと思います。
(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)
奥出雲フォーラム
去る2月15日に、「えひめ地域づくり研究会議」と当センターなどが共催して行いました「希望の島フォーラム」は、えひめ地域づくり研究会議の会員でもあり、当センターとも縁がある兼頭一司さんが中心となって上島町で行いました。
兼頭さんはJターンにより、上島町にご家族とともに移住して地域づくり活動を行うことを決意し、現在、弓削島に「島でカフェ」を立ち上げて、日夜奮闘中であります。
その「島でカフェ」の様子は後日この研究員ブログでご紹介することとして、ここでは別の話題をひとつ。
兼頭さんは財団法人松下政経塾の卒塾生で、松下政経塾の塾生は卒塾するためにはこのようなフォーラムを開催することが条件になっているそうでして、兼頭さんもこの「希望の島フォーラム」は卒塾フォーラムという位置づけでもありました。
そんな「希望の島フォーラム」の参加者の中に、松下政経塾の塾生で兼頭さんの後輩にあたる島根県出身の塔村さんという方がおられました。
塔村さんも同じくふるさと島根の地域活性化のためにがんばりたいとの熱い想いをもっておられ、このほど塔村さんご自身の「奥出雲フォーラム」と題した「卒塾フォーラム」を開催するということでご案内を頂戴し、あわせてフォーラムの周知をしていただけないかとの依頼も受けましたので、ここでご紹介いたします。
記
「奥出雲フォーラム」
~奥出雲の未来を一緒に考えてみませんか?
日時 平成20年12月20日(土)14時~17時30分
場所 カルチャープラザ奥出雲 大集会室
参加費 フォーラム300円(高校生以下無料) 交流会3,000円
主催 財団法人松下政経塾
<おもな内容>
14:15 塾生発表「奥出雲の未来のために」
(松下政経塾第27期生 塔村俊介)
14:45 パネルディスカッションⅠ
「私たちは地域の元気な未来をこげんやってます!」
パネリスト
・福間敏(内閣府地域産業おこしに燃える人)
・河内山哲郎(山口県柳井市長・道州制ビジョン懇談会委員)
・福原慎太郎(島根県益田市長)
16:10 パネルディスカッションⅡ
「奥出雲をどげなきゃせないけん!
未来を本気で考えるトークバトル」
パネリスト
・安部 悟(有限会社タイノス代表取締役)
・石田信雄(石田食品代表)
・内田咲子(有限会社松葉屋常務取締役)
・三澤 誠(有限会社エヌ・イー・ワークス取締役社長)
お問い合わせ先 財団法人松下政経塾まで
(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)
地産地笑市~柳井町商店街~
12月9日付の新聞各紙の地方欄に、松山市柳井町商店街の若者たちが開設した産直市「地産地笑市」が1周年を迎え、記念イベントを12月10日まで開催している記事が掲載されていました。
この若者たちのグループ「STEADY CREW」については、すでに「舞たうん98号」でご紹介しておりますので、詳しい活動については割愛することとし、さっそくイベントの様子を拝見しようとのぞいてきました。
訪れたこの日はあいにくの雨模様ということもあり、ひとの流れもまばらでしたが、買い物客に対して元気に応対しているスタッフのみなさんがとても印象的でした。
この産直市は大洲市肱川町の産直市ということもあり、特産品でもある肱川ラーメンや炭焼きシイタケの販売のほか、大洲地方の特産品のさといもをつかった「里芋コロッケ」なども店頭に並んでおり、さっそく「里芋コロッケ」を購入いたしました。
気になるお味については、普通のじゃがいものコロッケとは違い、里芋のねばりや味が感じられ、たいへん美味なコロッケでした。ぜひご賞味あれ。
さて、この「地産地笑市」のような産直市は、久万高原町のアンテナショップや愛南町の道の駅のアンテナショップなど、探すとけっこうあるようです。内子のフレッシュパークからりの産直市もあるようです。それだけ県内最大の消費地である松山にマーケットとしての魅力があるということなのでしょう。
また、そのいっぽうで、愛媛県の食料自給率は平成18年度の統計ですが、カロリーベースでいうと全国平均を下回る37%であるということをご存知でしょうか? 私も最近まで知らなかったのですが、この事実をしってたいへん驚きました。
この食料自給率をあげるためには、もちろん消費者が県産品を購入しなければなりません。そうなると県内最大の消費地である松山に、このような産直市が数多くうまれるのもある意味において当然なのかもしれませんね。
(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)
宇和島シゴト人バスツアー報告会&キャリア教育講演会
宇和島市(担当課:市教委生涯学習課)では、今年度から愛媛県が創設した「新ふるさとづくり総合支援事業」を利用して、市内の高校生を対象にした「キャリア教育」の視点による地域連携事業を行いました。
現在、地域コミュニティ力の低下がさけばれている中で、特に子どもたちを取り巻く課題として、中学・高校と上の学校に進むにつれて地域との関わりが希薄になってきていることがあげられています。
そこで、宇和島市では、高校生の一番関心の強い「自分の将来のこと=キャリア」を切り口に、市内の多方面で活躍されている社会人の方々から自分たちの高校時代のこと、ふるさと宇和島への想い、仕事に対する姿勢、将来の夢などについて高校生に語っていただき、高校生に自分の将来のことや、ふるさと宇和島のことについて考えるきっかけを提供する事業を行うことにしました。
宇和島シゴト人バスツアーと名付けられたこの事業は、宇和島市内にあるすべての高校の協力のもと、市内の高校生約50人が市内の事業所や社会人を訪問して話を聞くというもので、去る9月9日に実施いたしました。
今回、そのバスツアーの様子を紹介し、またバスツアーで紹介しきれなかった社会人の方のインタビュー記事を掲載した報告書が作成され、このたび下記のとおり開催される報告会で参加者に配付されるそうです。
また、この事業の大きな特徴のひとつは、大学のインターンシップを利用して、大学生にこの事業の企画・運営に参画してもらっている点です。この事業には5名の大学生が参画しており、そのうち4名は宇和島市外出身の大学生です。
対象となる高校生と年も近い大学生の視点を取り入れ、なおかつ「ヨソモノ」から見た宇和島の姿を高校生にも伝えていくことができたらという意図があり、高校生に紹介する社会人への取材を行った夏休みには、市民有志の方の家にホームステイをしながらインターンシップを行ってくれたそうで、そんな大学生のインターンシップ報告も兼ねてこの報告会は開催されます。
なお、報告会の終了後には「ジョブカフェ愛WORK」にも協力を依頼して、社会人を対象として「キャリア教育」の講演会や交流会を行うことにしていますので、あわせて興味のある方は、宇和島市教委までお問い合わせください。社会教育関係者の方、学校関係者の方は特に参加する価値アリだそうです。
記
と き 平成20年12月13日(土)15:00~17:30
ところ 宇和島市役所2階大ホール
内 容 ①15:00~16:00 「宇和島シゴト人バスツアー」報告会
・大学生による実施報告
・参加高校生の感想
②16:00~17:30 キャリア教育講演会
・県内のキャリア教育実践の事例紹介
・現代の若者の就職事情から見えてくるもの
対 象 ①市内高校生、社会人
②社会人のみ
その他 講演会終了後には交流会もあります(事前申込制)
【お問い合わせ先】
宇和島市生涯学習センター 担当:中村
TEL 0895-25-7514
(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)


