佐伯に行ってきました
前回の研究員ブログの続きです。臼杵市で町並みなどの視察研修を行った後、大分県佐伯市を訪問いたしました。
ちなみに、佐伯市は「さいきし」と読みます。みなさん、「さえき」ではないそうですのでお気を付けください。 って、こんなことを書いたら私が勘違いしていたことがバレバレですね。
佐伯市に到着いたしましたのが夕方でしたので、佐伯市教育委員会の教育委員長をされている宮明邦夫さんのご好意により、まちづくり関係のみなさんと親睦会を行いました。

懇親会の様子

立派な舟盛り!豪華です。
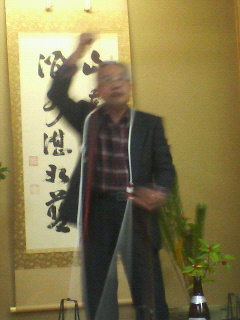
余興で手品も登場しました。みなさん芸達者です。

それで、親睦会で勢いがついて佐伯市役所の方の行きつけのお店へ全員で移動。ここで登場いたしましたのが、佐伯市が誇るB級グルメ「ごまだしうどん」。
この「ごまだしうどん」の「ごまだし」とは、 焼いたエソ類などの魚の身、胡麻、醤油等を混ぜ、擂り潰して作られる郷土料理のことです。湯に溶いてうどんを入れ、「ごまだしうどん」として食すのが一般的で、この「ごまだしうどん」は農山漁村の郷土料理百選にも選定されています。一同、おいしくいただきました。
翌日は、宮明さんから佐伯のまちづくりについて講義を受けました。宮明さんは教育委員長のほかに商店街の会長もされ、さまざまな公職につかれてまちづくりに取り組まれていますが、その原点は県南落語組合とよばれる落語により地域づくり活動であるとのことです。
宮明さんからは笑いをまじえながら、とても示唆に富んだお話をうかがうことができましたので一部をご紹介いたします。
・コンセプトのあるまちづくりを。
佐伯市に限らず地域の連帯性が弱くなっている中、特に商店街は希薄だと感じます。そんな中で郊外にショッピングモールができて人気が出てお客がとられるのは当たり前で、それはショッピングモールにはコンセプトがしっかりとあるからだ。ショッピングモールはお互いの顔が見えるという点では弱い部分であるが、そういったお互いの顔が見えるショッピングモールができたら商店街はとても勝つどころか生き残ることすらできないだろう。
また、商店街の成り立ちは自然発生的にお店をたちあげており、商店街としてのコンセプトがあるわけではなく、現在多くの商店街がシャター街となっているのは、玉石混交のお店があるからだと言える。
であるから、言い換えればシャッター街となった今がチャンスともいえる。コンセプトをもった商店街をしっかりとつくることができれば、かならず商店街が生き残ることができるともいえる。
自分の店は薬局だが、自分の両隣3軒がシャッターがおりていたお店となっていたので、友人などのツテを使い自己努力で自分の両隣の空き店舗に地主を説得して、友人の医者に整形外科医院と眼下医院を開業してもらった。そうなると医薬分業だから自分の店にも利益がでるようになった。
そして、そのもうひとつあいていた空き店舗にはその両隣の医院の待合室ということでスペースを設けて、患者や住民たちの交流の場をもうけた。こうすることによりコンセプトを持った商店街づくりができるようになっていった。
きっとコンセプトのある商店街づくりとはこういうことなのだろうと思う。
・できないことは人にやってもらう
人にはやれることとやれないことがある。だからこそ、それぞれの得意分野をうまく融合させることが大事で、さきほどの自分の薬局と両隣の医院の関係にも似ている。何でもすべて自分がマルチになってやる必要はないわけで、自分ができないところは、できる人にやってもらい、それぞれが役割分担しつつ、また切磋琢磨しながら高めあう、そういうようなグループをつくることが大事である。
宮明さんに貴重なお話をうかがったのちは、物産所に立ち寄ってお土産を購入するなどして、佐伯市の古い町並みを市の観光ボランティアガイドの方によりウォッチングしました。
トンカツならぬ「ブリカツ」です。ブリカツ丼なるものもありました。
ボランティアガイドさん。もとはバスガイドさんということで、流暢なガイドにみなさん聞き惚れておりました。ガイドの途中の雑談にでてくる佐伯の方言が素朴でとっても素敵でした。
ガイドの様子
佐伯市も古い街並みが残っています。
マンホールには国木田独歩の詩が。
佐伯市と言えば、なんといっても国木田独歩です。どんな人だったかは知らない人は調べてくださいね。
ちょうど、塀を修復している工事現場を見ることができました。
お家のところどころに飾り瓦があり、ウォッチングにもたまらないところです。
ところどころかわったおうちもあります。
途中で抹茶の休憩なども少々・・・。
ガイドさんと一緒に佐伯のおいしいお食事と美しい風景を堪能いたしました。また、成人式の新成人に古い街並みで写真撮影をするといった仕掛けや、ミニ四国八十八か所を発掘しようとするなど、ガイドさんの地域づくりにかける熱い思いも聴かせていただきました。
愛媛から海をへだてたところにある大分県。特に佐伯市や臼杵市などはあまり行く機会がないところではありますが、ふたつの市のまちづくりから学ぶことが多かった研修だったように思います。
(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)
上須戒さくらまつり
最近、あたたかくなり、春の訪れを感じるようになってきました。先日、桜の開花予測時期が報道されていましたが、これから桜が見ごろの季節となってきますね。
さて、そんな中で、大洲市の上須戒公民館の方からぜひイベントの告知をしてくださいというプッシュをうけましたので、今日の研究員ブログはイベント開催のご案内です。
大洲市の上須戒地区では、第5回上須戒さくらまつりを下記の日程で開催いたします。ちょうど桜も見ごろの時期だそうですので、興味のある方、ぜひご参加ください。
上の写真は昨年の様子ですが、私も公民館主事をしていた関係で経験があるのですが、こういうイベントごとをする際に「もちまき」は必須事項のようで、もちまきをすると告知をすると人が必ずやってくるという鉄則があります。しかし、なぜ人は「もちまき」に弱いんでしょうかねえ。ま、どうでもよい話ですが。
記
名称 第5回上須戒さくらまつり
日時 平成20年4月6日(日)(雨天決行)
午前10時~午後3時
場所 大洲市上須戒丙576番地1
上須戒ふれあい広場(旧大洲少年自然の家)
主催 上須戒地域振興協議会
内容 地元農産品と花木の販売、うどんなどのバザー、
大洲農業高等学校吹奏楽部の演奏、もちまき など
<バザー出店予定>
じゃこてん・巻き寿司・いなり寿司・ちらし寿司・みたらし団子・綿菓子・ビール・ジュース・きねつき餅・焼きそば・揚げ餅・こんにゃく・コーヒー・フランクフルト・イカ焼き・うどん・いのしし鍋・焼肉・パットライス
<イベント予定>
大洲農業高等学校吹奏楽部 11:30~
※ 大洲農業高等学校吹奏楽部の演奏は、雨天中止とします。
もちまき 13:00~
問い合わせ先:愛媛たいき農業協同組合上須戒支所
TEL(0893)26-0021
上須戒公民館 TEL(0893)26-0146
なお、このお祭りに参加されます場合は、環境保全とごみ削減を考えるための「はじめの一歩」として、マイ箸(はし)、マイバックを持参していただいて、エコに協力してほしいということでした。ちなみに、大洲市からの提供で130個限定でエコバックを配布する予定だそうです。
(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)
臼杵に行ってきました
去る2月23日(土)・24日(日)の両日、えひめ地域づくり研究会議の会員有志のみなさんと一緒に大分県臼杵市と佐伯市まで先進地視察旅行に行ってまいりました。
今回の「研究員ブログ」は、そのうち臼杵市のまちづくりについて学習した様子をご報告いたします。
訪問したこの日、臼杵市ではちょうど社団法人日本建築士会連合会まちづくり委員会が主催の「第5回まちづくりセミナー」が開催されており、私たちもその一部だけですが参加させていただきました。
このセミナーは社団法人日本建築士連合会が、建築士のまちづくりに携わる専門性や職能の強化と今後のまちづくり活動の発展に資することをめざして開催しています。
今回の臼杵市でのセミナーでは、臼杵のまちなみをどう保存して活用していくかという事例報告や現地視察から学び、参加者同士による意見交換を通して今後のまちづくりの参考にする内容となっていました。

ちなみに、この日、海は大しけ。臼杵に向かう船はかなり揺れました。
話を戻しまして、臼杵に到着して午前中は臼杵市の図書館にあります(これもまた古民家風の建物で素敵)会場で臼杵市のまちづくりの事例報告と、質疑応答の様子を見学し、昼食をはさんで午後からは大分県職員でもある斉藤行雄さんのご案内で臼杵の古い町並みを視察し、また臼杵のまちづくりについてのお話をおうかがいしました。

午前中のセミナーの様子

臼杵の商店街。臼杵は景観にすぐわないとしてかつてあったアーケードをはずしています。

昼食の場所「ポルト蔵」と呼ばれるところ。かつて蔵だった施設を改装したお店だとか。

この日の昼食メニュー(郷土料理でした)

マンホールは臼杵市がキリシタン大名「大友宗麟」とゆかりのある土地であることから「南蛮船」をイメージしたものになってます。

ここ何とスーパーマーケットなんです。ちゃんと景観に配慮したつくりになっているんですね。

石畳の道が何とも風情がありますね。

これもまた「修景」のひとつ。水道管を見えないようにするために、管を石で囲んでしまっています。

こちらは臼杵らしく「竹」で管を囲っています。

カーブミラーも何とも素敵
さて、訪問して一番印象的だったのは臼杵の町並みを保存していく運動として、古民家を買い取るということをしているということでしょうか。保存運動をしている人が古民家を買い取ってそれをリフォームして住む。そういうことが臼杵で取り組まれています。

古民家を買い取ってリフォームされた家。ここは見晴らし良い高台にありました。

上の家にある書斎。何とも素敵。こんな書斎がほしいです。

自然石を利用した壁の家。何とも風流な・・・。

その家の書斎。うらやましすぎます・・・。
そんな古民家を再生した家を何軒か拝見しましたが、どの家も住みたいなあと思わせるようなところばかりでした。こんな書斎がほしいと思うのは私だけでは決してないはずです!
こういった古民家を買い取って町並みを保存するということは経済的な側面が大きく左右されますのでなかなかできることはないと思われます。
臼杵の場合は建築士さんたちが中心となって景観保存をされているそうですから、古民家を買い取っても自分たちで設計して作りなおせばよいわけですから、通常の古民家買い取りとは若干意味合いが違いますが、そういった取り組みができるということ自体が、たいへんすごいことだなあと感心いたしました。
また、臼杵といえば何といっても「竹宵」でしょうか。臼杵の町並みに竹の行燈を設置して、一部は市民から公募して設置したオブジェのような美術色の強い竹の行燈もあったりするなど、町並み全体が幻想的な風景を醸し出すイベントで、現在はNPO法人が中心となって運営されているそうですが、この竹宵は大分県内外から多くの観光客が訪れる人気のイベントです。
そんな竹宵の竹ですが、毎回、竹炭や粉砕して肥料にして有機野菜を栽培し、毎回設置する竹はすべてその年に伐採したものを使っていることをはじめて知りました。
これは竹林の被害で山が荒れることについても少しは防ぐこともできますし、なかなか練られたシステムではないでしょうか。臼杵のまちなみの修景も含めて「臼杵のまちづくり」に学ぶことはたいへん多かったように思います。
(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)
がんばれ、愛媛FC!
いよいよ先週の土曜日からサッカーJリーグの2008シーズンがはじまりました。愛媛県に在住する者としてはやはり愛媛FCの応援をせずにはいられません。愛媛FCはJ2に参入して3年目のシーズンとなるわけですが、今年はぜひ上位をめざしてがんばってもらいたいものです。
といいながら、恥ずかしながらまだニンジニアスタジアム(略称:ニンスタ)にも行って試合観戦をしたことが1回しかないんですよね。今度のシーズンは何回かは行ってみたいものです。
ちなみに、ニンジニアスタジアムとは愛媛県総合運動公園陸上競技場のネーミングライツを取得した伊予市の会社の名前から来ています。これから3年間は「ニンスタ」の愛称で親しまれていくことでしょう。マスコミ報道をみていると除幕式の様子も放送されていたようです。
今回は、愛媛FCを応援する意味を込めて、コンビニチェーン店のローソンさんが愛媛県内限定で販売している『ビッグトリー弁当』をご紹介いたします。
このお弁当、愛媛FCに勢いをつけてもらいたいという意味合いでしょうか、ゴーゴーゴー(Go!Go!Go!)というゴロあわせのようで、お値段は555円になっています。販売期間は3月中のようです(県内限定)。


お弁当の中身ですが、大きなチキン南蛮、要するにビッグな鶏がはいっているのでビクトリーというわけで、スタジアムにいけない方はこれを食べて愛媛FCを応援しましょう(笑)
あと、お味はかなりのがっつりのボリューム系ですので女性には不向きのような感じがしますが、若い学生さんたちにはちょうどいいお弁当かも。
さて、気になる愛媛FCの開幕戦ですが「漱石ダービー」と称して「ロアッソ熊本」との対戦で、2-1で見事に開幕戦を勝利で飾りました。この調子でがんばってもらいたいものです。がんばれ! 愛媛FC!
(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)
研究員の休日
四万十ドラマという株式会社が高知県四万十町にあります。これは旧窪川町、旧大正町、旧十和村の3町村が出資してできた第3セクターで、14年前に設立されました。
この四万十ドラマという会社、地域づくりの現場でかなり有名なところで、特に地域の特産品をヒット商品にした畦地履正さんはその筋では有名な方です。
もともと、私自身はセンターに来るまで恥ずかしながら全く知らなかったのですが、センターの雑誌ECPRを拝見して、四万十ドラマという会社があること、そこに畦地さんという方がいることをはじめて知りました。
双海町の若松進一さんは夕日というブランドを確立するためにストーリーをつくりましたが、この畦地さんは四万十川というブランドをうまく活かすためにそこにストーリー(ドラマ)を用意したということでしょうか。
最初はアユ・川エビなど地元のいわゆる代表的な産物に「四万十」というブランド名を付けて売り出したそうですが、そう簡単にはうまくいかなかったそうです。
そこで畦地さんは、四万十ならではの商品開発のヒントをつかもうと地域の生産者を訪ねて回り、まずは話を聞くことにしたそうで、その中で地域にはいろいろなオンリーワンの技能をもつ人(たとえば川漁師など)がいることに気が付いたそうです。
そして、畦地さんはモノではなく、ヒトに注目して、そんなオンリーワンの人たちと組んで何かできないかなと考えたそうで、最初に生まれたのは地元の木工職人と組んでできた「四万十のヒノキで作る小さな板」でした。
これは香りを楽しむ商品でしたが、全国各地にこのようなものはあり、どのようによそにはない「付加価値」をつけていくか、そこに畦地さんは苦心して、昔ながらの焼き印やヒノキの油で浸すなどの商品改良を行うとともに、販売方法もどうしたらよいのかがわからないので、まずは「四万十川のファンクラブ」の会員を全国から募り、会費をとって情報誌やさまざまなイベントに参加できる仕組みをつくりあげ、その会員さんに新商品を会報の付録としてつけたそうです。
そうすると、企業の販促用のプレゼントや結婚式の引き出物につかえるという反応がかえってきて、それをヒントに銀行や自動車販売会社に売り込みをかけると、順調に売り上げを伸ばして大ヒット商品となったとのこと。
そのほか数多くのヒット商品を飛ばしている四万十ドラマ。2月21日付の日経新聞には高知県産業振興センターが2007年度地場産業大賞を受賞したとの記事もあり、これは見ておかなければと思い、休日を利用して四万十ドラマが管理運営している道の駅「四万十とおわ」を休日を利用して訪問してきました。

昨年の7月にできたそうです

外観の様子。建物は県産材をつかってます。

店内の様子。さまざまな特産品が並んでました。

しまんとバーガーなるご当地バーガーもありました。

じつはこの地方はお茶どころです(写真は緑茶のアイス)

道の駅の裏は美しい川の風景を眺めることができます。
(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)


