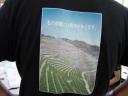第26回地域づくり団体全国研修交流会愛媛大会実行委員会設立
9月4日(火)、西予市中央公民館において、第26回地域づくり団体全国研修交流会愛媛大会実行委員会の設立総会が開催されました。
この「地域づくり団体全国研修交流会(以下、全国大会)」は、全国の地域づくり活動に携わる関係者が一堂に会して研修や交流を図ることを目的に毎年1回開催されており、平成20年度に愛媛県で開催することが内定しています。
この全国大会は、開催県において実行委員会を組織して実施していますが、この大会のメインとなる分科会の開催にあたっては、地域づくり団体が地元市町のサポートを得ながら企画・運営する形態になっており、愛媛県ではこの大会の開催を「南予活性化策のひとつ」として位置づけて、平成18年度より関係市町のまちづくり担当課の皆様と検討・協議をすすめてまいりました。
また、この全国大会は、全体会の中で、次期開催県があいさつとともにPRを行うのが通例となっており、本県も19年度の茨城大会において、次期開催県のPRを行うことになっています。
そこで、 茨城大会においてより効果的なPRを図り、また愛媛大会を実りある大会にするために、開催前年度である今年度から実行委員会を設立し、愛媛大会に向けて具体的な準備をすすめていくこととなり、9月4日に設立総会を開催する運びとなりました。
今回、実行委員として参画していただいたのは、南予を中心とした県内15の地域づくり団体の代表者のみなさんと、その団体所在地の市町まちづくり担当課の職員のみなさん、その他の関係者のみなさんの合計34名で、設立総会のこの日には32名の実行委員の方々にご出席いただきました。
※実行委員会の様子
実行委員会では、まず実行委員会の規約(案)が承認された後、規約に基づいて役員が選任され、実行委員長には「えひめ地域づくり研究会議代表運営委員」の若松進一さんが選任されました。
※実行委員長の若松さん
その後、実行委員長の司会のもと、事務局である当センターから実行委員会の事業計画(案)、予算(案)が提出され、それぞれ審議の後原案の通り承認され、今後の実行委員会の開催スケジュール等を確認しました。
なお、実行委員会事務局では、愛媛大会に関する情報については「実行委員会NEWS」というページを新たに当センターのHP内に開設し、実行委員会の会議の様子のほか、分科会を運営する団体のみなさんに関する情報や準備作業の様子などを発信していき、少しずつ愛媛大会を盛り上げていく予定ですので、そちらもあわせてぜひご覧ください(実行委員会NEWSのページは9月10日に公開予定です)。
また、この実行委員会の様子は9月6日付の愛媛新聞に紹介されるとともに、若松進一さんのブログでも記事紹介されていますのであわせてご覧ください。
(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)
段畑の背中
先日、「地域づくり人養成講座」の仕事で宇和島市遊子の水荷浦段畑に行った。よく考えると水荷浦の段畑に来るのは二年ぶりだが、今年は、全国で三例目という重要文化的景観に指定され注目を集めている。しかし、いつ見ても凄いの一言である。
昔の人達が建てたものや作ったものを見ると、人の力は凄いなぁとつくづく感心する。高度な科学力に基づく現代技術でもってしても修復や復元ができないものが多い。
民俗学者の宮本常一さんが、周防大島から対馬に移住した漁民達が港を築いた話を書かれていたのを読んだことがある。石を1つずつ海に入れては流され、ま た1つずつ海に入れて・・・という繰り返しで防波堤をつくり港を築いたという話である。この対馬の港づくりといい、遊子の水荷浦段畑といい、昔の人は経験 と繰り返しで不可能を可能にしてきたんだと思ったりもする。
その遊子で、先人が残した段畑を活かそうという人達と出会った。「NPO法人 段畑を守ろう会」の人達である。
講座では、副理事長さんである松田鎮昭さんから段畑にまつわる熱い想いを聞き、山内満子さんをはじ め女性部の皆さんの手づくりの段畑料理をいただいた。これらの料理はすべて地元で採れた物で手づくり、鯛バーガーなどの創作ものもあり、バラエティ ーに富みこれは作り込むといける。
最後に、 松田副理事長さんの背中をご覧あれ!
「私の故郷には段畑があります」と書かれ、馬鈴薯と段畑と空のコントラストが印象的。「ボクの村には”ごっくん”がある」という馬路村風のこのキャッチコピーがなかなか良く、聞くと農協がつくったらしいが、なかなかやるなぁ。
やっぱり男は背中ですねぇ~。
(文責 まちづくり活動部門 研究員 清水和繁)
第25回政策研究セミナーを開催しました
平成19年8月23日に第25回政策研究セミナーを開催しました。当日は大勢の皆様にご来場いただき、大変盛況な講演会となりました。
今回は、コミュニティ・ビジネスの伝道師であられる(有)コミュニティビジネス総合研究所 の細内信孝所長をお迎えして、「地域資源からビジネスへ~コミュニティ・ビジネスの可能性~」をテーマにお話をいただきました。私自身、「コミュニティ・ビジネス」という言葉を、本年4月に当センターに派遣されてから知りましたが、講師のお話や著書等に触れる中で、コミュニティ・ビジネスは、現在の社会情勢における地域活性化策として非常に有効なツールであるという印象を受けました。
また、今回のセミナーと合わせ、愛媛県研修所が主催された地域課題解決講座(~コミュニティ・ビジネスの手法を学ぶ~)にも参加し、実際に事業企画書や店舗(事務所)の計画書、資金計画書などを作成し、研修の最後には各班ごとにビジネスプランを発表するなど、実践的な内容について学習させていただきました。ある程度の予備知識を持って臨んだ研修でもあり、事業企画書や店舗などの計画書作成までは何とか進めたものの、資金計画書の作成段階で頓挫してしまい、起業の難しさと自分のビジネス感覚の無さを痛感いたしました。細内講師も、コミュニティ・ビジネスはある程度継続した活動でないと成果が出ないとお話されたように、ビジネスの視点における資金計画は重要なポイントであり、この部分が曖昧だとコミュニティ・ビジネスとして成立しないということです。
ちなみに、私の所属した班のビジネスプランは、上島町を舞台にした島の便利屋さん業、名付けて「かけはしサービス」(上島四島にコミュニティの橋を架けるという意味ですが・・・)を提案いたしました。内容を簡単にご説明しますと、島内の企業などの退職者で構成するNPO法人を立ち上げ、庭の草引き、買い物の代行、家具等の組み立て、雨戸の修理、レモンの収穫など、島内の身近な課題やニーズを住民から請け負うという事業でしたが、資金の調達方法など、資金計画の甘さをご指摘いただき、改めてビジネスの難しさと、マネジメント能力を有する人材の必要性を感じました。なお、 コミュニティ・ビジネスや講師についての詳細はこちらまで。
さて、次回の政策研究セミナーは、平成19年9月6日(明後日ですが・・・)NPO法人結まーるプラス理事長のかわべまゆみ氏をお迎えし、「2007なんよ地域づくり事例発表会」を開催します。地域づくり先進地での取り組み事例報告や、地域づくり実践者によるパネルディスカッションなどを予定しております。詳細並びにお申し込みはこちらまで。
(文責 企画研究部門 研究員 渡邊赴仁)
海のホタル
地域づくり人養成講座の第3回目は宇和島市遊子地区で行われ、受講生は遊子地区の景観を生かした地域コミュニティについて学習をした際に、地元の段畑を守ろう会の方から、段々畑を灯籠で照らすイベントの紹介がありましたが、その遊子地区に向かう道中にある宇和島市三浦地区でも、現在、養殖筏をイルミネーションで輝かせている取り組みをしています。
昼の養殖イカダ(左)と夜の養殖イカダ(右)
その取り組みをしているのは、三浦地区にある土居真珠さん。土居真珠さんでは、今年の夏から「海のホタル」と題して養殖筏をイルミネーションで輝かせています。この取り組みは養殖筏を使わない夏の時期しかできないもので、9月中旬頃までやっているそうです。
また、土居真珠さんでは、体験型観光ということで「真珠の核入れ体験」や「パールオーナー制度」など、宇和島真珠のブランド化とともに宇和島が誇る「真珠」を素材にしたさまざまな「地域おこし」の取り組みをされています。
この土居真珠の社長をしている土居一徳さんは、東京の大学やアメリカへ留学しているときに、宇和島の海と真珠の素晴らしさを知って、宇和島は世界にも通用すると思われたそうです。まちづくりの要素である「ヨソモノ」の視点を思い出しました。
また、地区の三浦漁協では、ブルーツーリズムで「シーカヤック」にも取り組んでいます。これは、宇和島市のすすめるグリーンツーリズム事業である「虹色ツーリズム」の一環として行われており、特に三浦地区や遊子地区のある三浦半島と離島をその重点地域に指定していることも影響しているようです。
このほかにも、三浦地区には地区独特の芸能である「鹿踊り」や、地域の人たちが農作物や水産加工品を出店する日曜朝市などもあり、遊子地区とともに地域活性化の要素や可能性をもっている地域だといえるでしょう。
なお、イルミネーションに関するお問い合わせは、土居真珠さんのHPを参照してください。
(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)
クラス会にふるさと学習を!
平成19年8月19日(日)付の愛媛新聞の読者投稿欄に、大阪府の60代の男性が「宇和島でクラス会を開催したときに、ふるさとの歴史を学習する講座をあわせて実施して、参加者に大変有意義なクラス会となった」という内容の興味深い投稿が掲載されていた。
これについて、宇和島市の対応をした職員に話を伺うと、以下のような経緯で講座を実施したそうだ。
・平成18年3月に先方から電話で学習の機会の提供の相談があり、市教委文化課が対応
・依頼者と応対担当者が電話等でやりとりをしながら講座の中身について協議
・依頼者は講座の会場となっている場所の下見や講座内容の協議に3度帰郷
・応対担当者は講義のレジュメを作成し、クラス会案内通知文書に同封してもらうようにした
・宇和島祭り(平成18年7月)にあわせてクラス会を開催し、約20名が1テーマ1時間の3テーマの講義を受講
・講座会場には宇和島市立歴史資料館(明治17年建築)の一室を使用し、郷愁を誘う学習会場だったこともあり参加者にはたいへん好評だった
・参加者の中には次のクラス会のときは歴史以外に宇和島の産業についても学習したいという要望もあがっている
さて、このような団塊の世代を含めた年配層が帰省した際に、せっかくふるさとに帰るのだからあわせて「ふるさとについて学習をしておこう」といったような「学習ニーズ」が実際にはどの程度あるかどうかはわからないが、団塊の世代の移住促進をも視野に入れた「帰省時のふるさと学習講座」は、意外に観光や生涯学習のメニューの1つとしては成立するかもしれないと思ったりもした。
なお、この取り組みのお問合せ先は宇和島市立歴史資料館(0895-23-2400)まで。
<豆情報>
宇和島市立歴史資料館は明治17年に宇和島警察署として建築され、のちに旧西海町役場として使われた時期もあり、平成4年に宇和島市住吉町に移築され、現在に至る。なお、建物自体が国の登録文化財にもなっており(愛媛県で最初の登録文化財)、現在は、常設展示のほかに高畠華宵大正ロマン館(東温市)と提携して館内で企画展示を実施している。
(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)