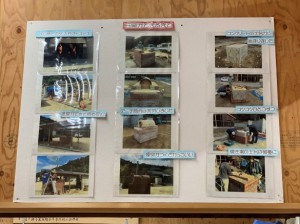西予市渡江地区で報告会を開催しました。
愛媛大学社会共創学部2回生の内藤考祐です。
私たち渡江チームは、ワーケーションや産品紹介を通した地域のPR動画の作成や、渡江産品のネット販売を行うためのサイト作成などを行っています。昨年の10月からのプロジェクトですが、来るたびに多くを学びながら楽しく渡江での時間を過ごせています。
そんな我々の活動も、集落活性化意識醸成支援事業として渡江に伺う最終回。2月19日金曜日、まだ少し雪が残る中の西予市明浜町渡江地区で、集落活性化意識醸成支援事業の報告会を行いました。実は報告会の前に、PR動画の締めくくりのワンカット、「極寒の海に飛び込む学生」を撮影しました。気になる方は、ぜひ渡江地区のPR動画をご覧ください。
報告会では、大学生が地域の方々のご協力を得ながら作成した渡江地区におけるワーケーションをテーマにしたPR動画や、渡江地区の紹介から産品を販売まで、渡江のことを満喫できるウェブサイト「とのえずかん」など、渡江地区で新たに行われてきた取り組みを、地域の方々の前で発表できる機会をいただき、今後の発展や、継続に向けての動きなど、報告会の中でたくさんの気づきを得ることができました。
今回の集落活性化意識醸成支援事業を通してつながっていったご縁を今後も継続していきながら、我々大学生として、渡江にできることを考えていきたいと思います。
東温市奥松瀬川地区で地域分析ワークショップに参加しました。
愛媛大学社会共創学部2回生の髙橋美結です。
去った12月8日(火)に、藤山浩所長をお招きして行われた、奥松瀬川地区の地域分析ワークショップに参加しました。
ワークショップの前半の部では、藤山所長が奥松瀬川の魅力を把握する為の、フィールドワークが行われました。そこでは、私たちが気づかなかった、藤山所長独自の視点から地域の方々への質問などがあり、一度通ったルートではありますが、見つけられなかった奥松瀬川の情報を得ることが出来ました。
前回と目立って変わった点は、ほっこり奥松で暖を取れる様にと、レトロなものが出現した事です。飾りじゃなく、現役で使用できるそうで、快適に使えるように手が加えられていました。そして、ログハウスの近くにもう一つ大きな建物を新しく立てていました。
ワークショップの後半では、藤山所長の地域分析結果が、奥松瀬川地域の皆さんに伝えられ、奥松瀬川地域の住民と藤山所長との間で意見交換などが行われました。
藤山所長の分析結果では、奥松瀬川地域には他の地域と比べても、魅力や活力などが十分にあり、奥松瀬川地域が目指す、移住についての考えも現実的に叶いそうであるとのことだったので、今回までの取り組みを踏まえて、これからの奥間瀬川の未来予想図を丁寧に描いていく、お手伝いをしていける事が出来ればと思いました。
西予市渡江地区で地域分析ワークショップに参加しました。
愛媛大学社会共創学部3回生の三宅です。冬の訪れを実感しながらみかんを食べる毎日です。私たち渡江班では、地区のPR動画作成や渡江産品通販サイトの作成など様々なプロジェクトに参加させていただいており、日々プロジェクトを通じて多くの学びを得ています。
さて、12月10日木曜日に、西予市明浜町渡江地区で一般社団法人持続可能な地域社会総合研究所所長の藤山浩先生をお迎えしてフィールドワークと地域分析ワークショップが開かれました。
13時から15時まで藤山先生と共に渡江地区を散策し,地区の特性を再確認しました。
15時から1時間半行われたワークショップでは、2015年から2020年の5年間の人口増減を基に、50年後の人口を男女別・年齢別に推計した人口分析の結果を踏まえた地区活性化の提案および意見交換を行いました。その中でも、最初に移住する人の印象が地域に与える影響や、人が楽しんでいる場所が持つ可能性のお話が印象に残っています。今回のワークショップでの知見を今後の活動に反映していきたいと思います。
これは、渡江の漁師薬師寺さんに頂いたタコで作ったタコ飯です。タコの旨みが出ていてとても美味しく出来ました。
最後に、お忙しい中「お灸に関するアンケート」にご協力いただきました渡江地区の皆様へこの場をお借りして感謝申し上げます。
伊方町豊之浦地区で地域分析ワークショップに参加しました。
こんにちは!
愛媛大学 社会共創学部3年 鶴岡です。
今回、伊方(豊之浦)班は、12月3日(木)に「田園回帰1%戦略」の著書で有名な、持続可能な地域社会総合研究所の藤山浩所長による地域分析ワークショップ(in 伊方)に参加しました。
ワークショップの前半は、藤山所長も一緒に、豊之浦地区でフィールドワークを行いました。
地域の活性化団体の方に案内してもらいながら、お寺や閉校してしまった小学校、商店などをまわり、豊之浦地区がどういう地域でどのような歴史をもっているのかを自分の足で歩きながら体験することができました。
実際、お寺の本堂の天井や壁に掛けられている絵には、「壇ノ浦の戦い」の絵や「七福神」を始めとする様々な絵があり、他の地域では見たことのないものでした。
地元の方々もこの絵には多くの謎があるといっていました!!
ワークショップの後半では、「豊之浦地区の人口分析結果について」現状のままで推移した30年後と何かしら手を加えた場合の30年後の差などに対しての考察などをしていただき、現在と未来の豊之浦地区について改めて考えることができました。
また、持続可能な地域づくりを行う上で「豊之浦地区」が具体的にどのような目標をもって地域づくりを行っていくべきなのか、どういう風に地域の交流の場をつくっていくべきなのかについてもお話していただき、とても勉強になりました。
その後の質疑応答でも、地域の見方や仕組みの作り方など細かいことまで教えてくださり、とても有意義な時間でぎりぎりまで質問が飛び交っていました!!
今回学んだことを活かして、今後の活動の糧にしていきたいと思います!!
今回の報告は以上です。ありがとうございました。
PS.藤山所長は地域の方を見つけるとすぐに声をかけてお話を聞き、仲良くなってお土産をもらっていました⁉
今治市吉海地区で地域分析ワークショップに参加しました。
こんにちは!
愛媛大学 社会共創学部3年 東です。
今治(吉海)班は、12月2日(水)に「田園回帰1%戦略」の著書で有名な、持続可能な地域社会総合研究所の藤山 浩所長による地域分析ワークショップに参加しました。
藤山所長の「吉海地区の人口分析結果について」のお話では、現状のままで推移した30年後と何かしら手を加えた場合の30年後の差などがよくわかりました。
また、ここ5年間で20代後半から30代前半の男性が約100人流入しているのに対して、20代女性が約50人流出していて、30代、40代でも流出が続いていることがわかりました。
地元の方は、造船場関連の働き手として男性が増えたのではないかとおっしゃっていて納得しました。今後は女性の働く場所に注目して調べてみたいと思いました。
午前中は、藤山所長も一緒に、吉海地区を見学しました。
まずは廃園になった保育所をNPO団体の事務所として使っている「吉海南保育所」
敷地内で育てている黒ニンニクを試食しました。
保温機で2週間程度保温した物なので、プルーンのようなネチャっとした食感!
ニンニクの風味が強いのに、甘い、、、
なんとも不思議な味でした(笑)
パンなどに塗っておつまみにもいいというのを聞いて、納得しました。
味が濃いので何かにつけたほうがいいです◎
続いて、オリーブ園へ。
第一回フィールドワークで来たときは、オリーブの実がなっていたのですが、今回は収穫が終わっていました。
そしてまたまた試食♪
オリーブの実をいただきました。
うっすら塩味で美味しかったです。
オリーブの実を味わって食べたことはなかったので嬉しかったです!
最後に「善根宿 蔵」
お寺参りをする方たちが泊まれるように空き家を改良して作った宿で、昔の建築様式を見ることができます。
学生はここを訪れるのは2度目だったのですが、
井戸を新発見しました。
井戸を見るのは初めてで、覗いてみるとちゃんと水が見えて感動しました!
次回のフィールドワークも楽しみです。
今治市吉海地区で第2回フィールドワークを行いました!
こんにちは! 愛媛大学社会共創学部二回生の小幡です。
11月18日(土)今治市にある大島の吉海地区にて「集落活性化意識醸成支援事業」の第2回フィールドワーク実習を行いました
今回の活動の内容としては、
1. Aコープ吉海店でのAコープの店長さん、実際にAコープに出品されている農家と以前大学でも貴重な話を聞かせてくださった大島ご出身の竹田さんを交えて聞き取り調査。
2. 現地の方(吉海支所の方、竹田さん、地域おこし協力隊の方、地元住民の方)にそれぞれ学生が分かれて事前に用意した質問を中心に聞き取り調査。
以上の2つを行いました。
Aコープ吉海店では地域の農家さんの大半が出品されており、曜日によっては市場がパンパンになるほど商品が並ぶそうです。また、吉海地区としては人口も減少傾向にありながらも運営の経営努力や他者にはない“Aコープらしさ”を追求する姿勢によりここ4.5年は売上をキープしているそうです。ただ、そんな状況でも吉海地区の人口の高齢化、減少。また生産者の高齢化という部分も顕著であり事実、Aコープに出品される農家さんのうち96%以上が60歳以上という状況でした。
ここから、高齢化が進むにつれ従来の農業スタイル(たくさん作って売る、それで生活する、がっつり稼ぐ)から小規模な経営スタイル(自分たちに必要な量+αで作り副収入を得る)に現地は変化していることに気づかされ、それら零細な農家さんをいかにして守っていくかが地域の産業や耕作放棄地等の問題にかかわってくると考えました。
後半の聞き取りでは私は地域おこし協力隊の兵頭さんにお話しをうかがうことができました。兵頭さんは東京や大阪で20年以上働いて暮されていましたが、都会の家賃の高さなどから老後に対して漠然とした不安を感じたことから地方への移住を考えるようになったそうです。自分も東京の出身であり、都会と地方の家賃の差には共感する部分が多くまた、老後に対する漠然とした不安(特に家賃)がある点は自分の両親と重なる部分が多くとても共感できました。そんな兵頭さんは大島に公共交通機関の空白地域が多すぎることや前職での知識経験を生かした“タクシー事業”や島に運動施設がないことや圧倒的なクルマ社会であることから島民の健康面にも課題を感じ、趣味の総合格闘技を通じて運動する機会を提供しようと“総合格闘技の教室を開こう”と計画、行動しているそうです。
今回のフィールドワークを通じてたくさんの方とお話しする機会があり大島だけではない今後の日本の農業への在り方を考えさせられ、人の生き方、人生設計の多様化というのを肌で感じることができました。また、課題というのは悪いこと、改善すべきことであり、そういうものはすぐに見てしまいがちです。その数ある課題の中から優先順位をつけて、選択と集中をして解決にむけて動くことが我々に求められていると感じました。
最後までお読みいただきありがとうございました
西予市渡江地区で第2回フィールドワークを行いました!
こんにちは。社会共創学部2回生の内藤です。
11月11日(水)に西予市渡江地区にて、「集落活性化意識醸成支援事業」第2回フィールドワークを行いました。
快晴の中、渡江地区のPR動画を撮影する際の撮影場所のロケハンを行うため、地域の中を回りました。潮が引いて出来た潮だまりには、イソギンチャクやウニ、カニなど多くの生き物がおり、広大かつ幻想的なミカン畑と、青く広がる美しい海のコントラストが素晴らしい、そんな渡江の豊かな自然を改めて肌で感じ取ることができました。
今の時期は、ミカンの収穫シーズンであり、地区のほとんどのミカン農家さんが収穫のために山に登っていたため、今後の話し合いの場にはなかなか足を運べないとのことでしたが、たくさんのミカンを差し入れて下さり、みんなでおいしく頂きました。
お昼ご飯は、青空の下、海を見ながらみんなで食べ、次回の撮影に関して構想を練っていきました。
ミカンのネット販売とPR活動の二本の柱で活動を行っており、次回からは、実際に撮影に入りますが、この時期の貴重なお時間をいただく以上、改めて気を引き締め、地域の方にご協力いただきながらも、私たちもより一層、渡江地区のお力になれるように、精一杯取り組んでいきます。
今回の報告は以上です。ありがとうございました。
東温市奥松瀬川地区で第2回フィールドワークを行いました!
こんにちは!愛媛大学社会共創学部3回生の嶽です。
10月28日(水)に東温市の奥松瀬川地区にて「集落活性化意識醸成支援事業」第2回フィールドワークを行いました。
まず始めに前回見学することが出来なかった「ほっこり奥松」の施設見学を行いました。
施設内に入りまず目についたのは壁に貼られた数十枚の写真で、「ほっこり奥松」建設時の写真やパン教室、竹細工教室、同施設と公民館にて執り行われた結婚式の様子を写した写真などが飾ってあり、自分もその場に居たかのように和やかな気持ちになれました。
次に、公民館に戻り奥松瀬川地域のネット環境についてや東温市の取り組みなどについて意見交流を行いました。各個人それぞれの理解が深まり、今後の奥松瀬について考える為の材料になったのではないかと思います。
そして最後に、スマホ教室を行い地域の方と親睦を深めることが出来ました。
スマホの使い方が分からない方、ラインを入れているが使っていない方。学生は1人1人丁寧に使い方を教え、最終的な目的であるライングループの作成を成し遂げることが出来ました!
自分も地域の方と繋がるべきと考え何人かにラインを教えて頂くことになったのですが…
「またよくよく勉強してから」と断られてしまいました(笑)次回に期待です!
地域の方と一緒に何かを行う楽しさを改めて実感できる良い機会でした。
今後もよりよい活動の為、地域の方と協力していこうと思います。
西予市横林地区で第2回フィールドワークを行いました。
先日11/4の横林地区訪問では、班に分かれて地域住民の方へのインタビューと地区内の巡回を行いました。
午前中は、横林地区で特に力を入れている椎茸栽培についてのご説明をいただき、また、地区内の唯一の商店であるふれあいショップの現状についてのインタビューを行いました。
椎茸農家さんから椎茸についての様々なお話をいただきましたが、栽培されている椎茸に強い誇りとプライドを持っていらっしゃることを感じ、感銘を受けました。
ふれあいショップでは、経営が難しくなってしまった現在までの経緯やどうにか存続させたいという強いお気持ちをうかがい、地区サポーターの学生として利用される方の為にもしっかりと向き合っていかなければならないと改めて感じました。
昼食には、釜戸で炊いた新米と椎茸のお料理をいただきました。初めての釜戸で炊いたご飯と肉厚な椎茸をとても美味しくいただきました。
午後は、3つの班に分かれて、農家さんや牧場に行きお話をうかがいました。
私は牧場に行きましたが、初めて自分の目で見るたくさんの大きな牛に最初は怯えていましたが、肉質を改良するための餌と水の工夫や、牛肉として出回るまでの流れをお聞きし、だんだんと情が湧いてきたのを覚えています。
新型コロナウイルスの影響での子牛の価格の変動に頭を抱えていると知り、今後の大きな課題の1つであると認識しました。
今回の訪問を通して私が一貫して感じたことは、人と人とのつながりの大切さです。近隣住民の方のことをお互いに気にかけ合うような関係性を目にして、椎茸農家の方もおっしゃっていた、他に何にも代えられない人の温かさがある、という言葉を身をもって肌で感じました。後継者問題やお店の経営難など様々な問題についてお聞きしましたが、それ以上に地域住民の方の心の温かさに触れたことが強く印象に残る訪問となりました。
次回の訪問でも、しっかりと知見を広げられるよう、力を注いでいきたいと思います。
伊方町豊之浦地区で第2回フィールドワークに参加しました!
こんにちは、愛媛⼤学社会共創学部2回⽣の伊藤です。
前回の訪問には2回⽣が授業の関係で参加できず、3回⽣の先輩⽅に任せっきり、頼りっきりになってしまいました。
そのため今回は前回の遅れを取り戻すべく、大きなやる気を胸に伊⽅町へ向かいました。
豊之浦地区に到着するとすぐに船に乗り込み、漁師の⽅が準備してくださっていた仕掛けを回収しに海に出ました。
この⽇は晴天にも恵まれ、初めての漁を前に私たち学⽣はとてもワクワクした気持ちでいっぱいでした。
さて、いよいよ仕掛けポイントに到着です。
事前に「ヌタウナギ」を獲ることは知っていましたが、大きな機械を使って仕掛けを引き上げる様⼦に私たちはまだまだ興奮していました。そして1つ⽬の仕掛けが上がってきました。
漁師の⽅がその仕掛けを開け、中から出てきたものをみると・・・
⼤量の「ヌタウナギ」が姿を現しました。
テレビなど画⾯越しで⾒たことはあったものの、やはり実物を前にすると気持ち悪いと感じる他ありません。
この後の仕掛けからも続々と「ヌタウナギ」が⽔揚げされてきました。
大きな夢を抱き海に出た私たちの純粋な⼼は、儚くも「ヌタウナギ」のヌルヌルのように⽩く濁ってしまいました。
数々の慣れない体験からの疲労を感じる中、公⺠館に向かい⼤学⽣が持ち寄った案をもとに意⾒交換を⾏いました。
その際に漁師の⽅がお刺⾝をご馳⾛してくださいました。
タイやハマチなど⼀⼈暮らしでは滅多にお⽬にかかれないものがあり、海での疲れを吹き飛ばすことができました。
お刺⾝の⼒もあってか、地域の⽅と現実的なお話をすることができました。
しかし、内容を詰めなくてはならない部分も多くあり、今後はより⼀層の頑張りが必要であると感じました。
次回以降はさらに気を引き締めて少しでも豊之浦地区のお⼒になれるように精⼀杯取り組んでいきたいと思います。
今回の報告は以上です。ありがとうございました。