トークサロン「限界集落と地域の再生」
3月25日(火)に、当センター主催でトークサロン「限界集落と地域の再生」を開催いたしました(共催:地方シンクタンク協議会)。
このサロンは、当センターが「課題別研究サロン」と題して、毎年1回、さまざまな地域課題に関して全県的なテーマを選定し、地域づくり関係者を中心に講師等を交えて少人数で話し合うといった形式で行われるのですが、今回は新聞紙上などでもよく取り上げられる、いわゆる「限界集落」がテーマということもあって、会場となったリジェール松山には、県内外からおよそ100名ほどの参加がありました。
サロンでは、最初に基調講演を行い、講師には「NPO法人ひろしまね」の理事長で、「限界集落」に関する数々の実践活動をされている安藤周治氏をお招きし、「暮らしを地域から組み替える~「もう一つの役場」の取り組みと期待 ひろしまねから~」と題して、NPO法人ひろしまねが実際にやれれている実践事例を通して、人口減社会を迎える今後の地域づくり活動のあり方についてご講演いただきました。
特に、今後の地域づくり活動を行う上での求められる人材像として、「新しい価値観をもつ人材の育成」が急務とし、「プロデューサー」「ファシリテーター」「コーディネーター」「タウンマネージャー」「コーチ」といった役割がそれぞれできる人材を育成していくことが重要だと述べられており、参加者の多くが納得されていたように思います。
安藤氏の基調講演ののちは、パネルトークと題して3人の語り部をゲストに招き、会場全体でテーマである「限界集落と地域の再生」について議論をすすめていきました。
今回、語り部としてお招きしたのは、西予市野村町の地域づくり団体「むらの新資源研究会『山奥組』」で、実際に中山間地域集落機能の維持について調査研究活動をされている三瀬武男さん、久万高原町でかつて消防長をされ、現在は久万高原町グリーンツーリズム推進協議会の会長をされている平岡新太郎さん、旧中島町(現:松山市)職員で、離島関係の各種委員やえひめ地域づくり研究会議の運営委員などもされている豊田渉さんの3名の方々。
3名の方からは、それぞれの地元における地域の現状と課題を簡単に説明していただき、その後、フロアからの意見や質問をもとめ、語り部や講師となった安藤さんを交えて熱のこもった意見交換が行われました。
そして、サロン終了後には講師の安藤さんや語り部の方をまじえた交流会が催され、参加した多くの方が情報交換と意見交換をしながら今後の地域づくりについて熱く語られていたようです。
(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)
「ふしんせつ」お遍路マップ
現在、四国四県で四国遍路道文化を世界遺産化しようという動きがすすめられていますが、このたび宇和島市生活文化若者塾「拓己塾」のみなさんが、当センターの「まちづくり活動アシスト事業」の助成を受けて、宇和島市内のお遍路さん向けのマップを作成しました。

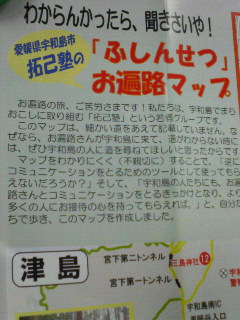
この「ふしんせつ」お遍路マップと名付けられたこのお遍路マップは、愛南町の40番札所観自在寺から宇和島市三間町にある41番札所龍光寺、42番札所仏木寺までの道のりのうち、旧宇和島市街地の地図を中心に掲載されています。
このマップのコンセプトは、ズバリ「不親切(わかりにくさ)」。
お遍路さんが宇和島に来て、道がわからない時には、ぜひ宇和島の人に道をあえて尋ねてほしいという考えから、細かい道を記載せずに敢えて「わかりにくく(不親切に)」したマップになっています。
不親切といっても、お遍路さんが利用しやすいように無料休憩所やコンビニ、公共トイレ、ガソリンスタンド、コインランドリー、銀行、交番、自動販売機といった基本情報はひととおり網羅されていますし、地図の裏面には拓己塾がオススメする「時代を巡ルート」「裏通りをのーんびり 食と文化探訪ルート」「川沿いを行く静かで安全なルート」の3つのルート設定を行っており、途中よくお遍路さんが立ち寄る飲食店や喫茶店の紹介など、お遍路さんには役立つ観光情報なども入っています。
というわけで、「わかりにくく(不親切)」というよりは、むしろ「おせっかい(情報満載)」マップのような形式になっていると言った方が適切でしょうか。
現在、拓己塾のみなさんはマップの設置場所について、お遍路さんが立ち寄ることの多い市内各所で交渉中とのこと。宇和島市内でこのマップを見かけたら、ぜひ手にとってみてください。
なお、マップの入手方法については、拓己塾の事務局がある宇和島市生涯学習センター(0895-25-7514)までお問い合わせください(午前9時から午後5時30分まで。月曜日が休館)。
(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)
第7回ふる里だんだん祭り
宇和島市遊子水荷浦地区で獲れる「早掘り馬鈴薯」は、日本一早く獲れる「新じゃがいも」と言われています。
じゃがいもの旬の時期はだいたい4月下旬から5月上旬ですが、遊子水荷浦地区の馬鈴薯は4月の初めには収穫できる上に、海と太陽、そして段々畑で育まれているため、ホクホクでたいへんおいしい馬鈴薯になります。
また、その収穫量もわずかなため、たいへん希少価値があり、宇和島市の推奨品にも指定されて非常に人気のある産品です。昨年はNHKの番組で紹介されたこともあって全国的に知られるようになり、あっという間に売り切れてしまって翌年の予約をした人もいるという「幻のじゃがいも」でもあります。
そんな日本一早く収穫されたと言われている新じゃがいもの収穫を祝う地元のお祭りが「ふる里だんだん祭り」です。
このお祭りでは馬鈴薯の即売会のほか、ステージイベント、子どもむけのイベント、馬鈴薯の重量当てクイズ、もちまき、といったさまざまなイベントのほか、じゃがいもを使った料理販売や郷土料理の販売が行われ、老若男女問わず楽しめる宇和島市の春のお祭りとなっています。
そんなお祭りが今年は下記のとおり開催されることになりました。遊子地区の美しい段々畑の風景と、そこで獲れた馬鈴薯、そしてその馬鈴薯を使った郷土料理を味わえるよいチャンスです。宇和島市遊子地区へ行ってみませんか?
記
1.と き 平成20年4月13日(日)10:00~14:00頃
2.ところ 宇和島市遊子水荷浦地区の特設会場(段々畑の前です)
3.内 容
①早掘り馬鈴薯の即売会
②郷土料理コーナー
③出店コーナー
④ステージイベント
⑤もちまき
⑥馬鈴薯重量当てクイズ
⑦子ども向けキッズパーク
⑧段畑ガイド
⑨その他
3.その他 遠方から遊子地区へ来場される方は、会場付近の駐車場スペースが限られていますので、乗り合わせで行くことをお勧めします。
(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)
持続可能な観光と地域づくりを考える
えひめ地域づくり研究会議が主催している今年度最後の「地域ミニフォーラム」が伊予市で開催されました。
これは、伊予市が1市2町で合併したのを機に、あらたに制作した観光ガイドブックである「い~よぐるっと88」が発刊されたことにともない、「持続可能な観光と地域づくりを考える」フォーラムと題して開催されました。
このフォーラムでは、地域の歴史・文化遺産を見直すツーリズムや環境・景観保全、農漁村との交流を求めるグリーン・ツーリズムに対する関心が高くなる中、固有の地域資源に光をあて、これからの魅力ある地域づくりと持続可能な観光政策のあり方を模索するため、以下のスケジュールで行われました。
①基調講演
②スライド解説
③パネルディスカッション
①の基調講演では、松山大学経済学部の鈴木茂教授が「『観光立国』と地域観光政策」~愛媛の観光の課題~と題して、愛媛県の現状や海外の事例をもとにお話をされました。
先生の話の中で特に印象的だったのは、都市と農村の格差のお話です。
日本の場合、農村は都市に人、物を供給している割に都市から農村へはあまり供給されていないという事実がある一方で、欧米の場合は都市住民は余暇を農村で過ごすというライフスタイルが定着して経済活動として農村も潤っており、日本も余暇を農村で過ごすというライフスタイルが確立されれば、「都市と農村の格差」という問題もなくなってくるのではないかというお話が印象的でした。
②のスライド解説では、えひめ地域づくり研究会議の岡崎事務局長が、伊予市歴史街道と題して、伊予市のあまり知られていない文化財を紹介し、「埋蔵文化財」とは土の中に埋まっている文化財のことをさすが、それとは別に住民自身がものの価値に気が付いていない文化財もまた、「埋蔵」文化財であるというお話は、みなさん納得されていたように思います。
③では、えひめ地域づくり研究会議の運営委員をされている門田さんがコーディネーター役、基調講演をされた鈴木先生がコメンテーター役として、「い~よぐるっと88」の執筆に関わった伊予市の住民の方3名(旧伊予市、旧中山町、旧双海町からそれぞれ1名ずつ)と、観光カリスマでもある若松進一さん、伊予市産業経済課の米湊さんをパネリストとして、「これからの伊予市・観光まちづくりへの提案」と題して、パネルディスカッションが行われました。
パネルディスカッションでは、実際に本の編集に携わった方の苦労話や、編集の成果などが話し合われ、なかなか活発な議論ができていたように思いますし、途中に笑いもおきるなど参加者も非常に身近に感じながらのパネルディスカッションができたのではないでしょうか。
その議論をごく簡単にまとめますと、以下の5つになるでしょうか。
(1)行政と民間が協力してつくることができた(協働の視点)
(2)普段何気ないものに価値があることがわかった(発見と再発見)
(3)高齢者の知的エネルギーをもっと活用すべき
(4)新しい観光メニューの可能性を感じることができた
(5)伊予市の観光情報が発信できた
もっとも印象的なのは、これまで市町村合併でメリットよりもデメリットばかり表面化されている中で、伊予市の場合は住民自身が調査をし、文化財を発掘して整理を行うという行為そのものが、地域づくりを行う上でもたいへん重要であるということでしょう。
また伊予市は市町が合併したことによって「町(旧伊予市)」・「山(旧中山町)」・「海(双海町)」という、それぞれ異なる地理的な特徴をもつ自治体が合併しており、それをうまく活かさない手はないということです。
今後の伊予市は「観光」という側面で、合併した強みを見出していくということがうかがうことができたフォーラムだったように思います。
(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)
佐伯に行ってきました
前回の研究員ブログの続きです。臼杵市で町並みなどの視察研修を行った後、大分県佐伯市を訪問いたしました。
ちなみに、佐伯市は「さいきし」と読みます。みなさん、「さえき」ではないそうですのでお気を付けください。 って、こんなことを書いたら私が勘違いしていたことがバレバレですね。
佐伯市に到着いたしましたのが夕方でしたので、佐伯市教育委員会の教育委員長をされている宮明邦夫さんのご好意により、まちづくり関係のみなさんと親睦会を行いました。

懇親会の様子

立派な舟盛り!豪華です。
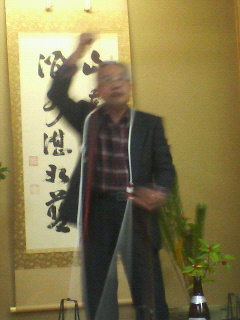
余興で手品も登場しました。みなさん芸達者です。

それで、親睦会で勢いがついて佐伯市役所の方の行きつけのお店へ全員で移動。ここで登場いたしましたのが、佐伯市が誇るB級グルメ「ごまだしうどん」。
この「ごまだしうどん」の「ごまだし」とは、 焼いたエソ類などの魚の身、胡麻、醤油等を混ぜ、擂り潰して作られる郷土料理のことです。湯に溶いてうどんを入れ、「ごまだしうどん」として食すのが一般的で、この「ごまだしうどん」は農山漁村の郷土料理百選にも選定されています。一同、おいしくいただきました。
翌日は、宮明さんから佐伯のまちづくりについて講義を受けました。宮明さんは教育委員長のほかに商店街の会長もされ、さまざまな公職につかれてまちづくりに取り組まれていますが、その原点は県南落語組合とよばれる落語により地域づくり活動であるとのことです。
宮明さんからは笑いをまじえながら、とても示唆に富んだお話をうかがうことができましたので一部をご紹介いたします。
・コンセプトのあるまちづくりを。
佐伯市に限らず地域の連帯性が弱くなっている中、特に商店街は希薄だと感じます。そんな中で郊外にショッピングモールができて人気が出てお客がとられるのは当たり前で、それはショッピングモールにはコンセプトがしっかりとあるからだ。ショッピングモールはお互いの顔が見えるという点では弱い部分であるが、そういったお互いの顔が見えるショッピングモールができたら商店街はとても勝つどころか生き残ることすらできないだろう。
また、商店街の成り立ちは自然発生的にお店をたちあげており、商店街としてのコンセプトがあるわけではなく、現在多くの商店街がシャター街となっているのは、玉石混交のお店があるからだと言える。
であるから、言い換えればシャッター街となった今がチャンスともいえる。コンセプトをもった商店街をしっかりとつくることができれば、かならず商店街が生き残ることができるともいえる。
自分の店は薬局だが、自分の両隣3軒がシャッターがおりていたお店となっていたので、友人などのツテを使い自己努力で自分の両隣の空き店舗に地主を説得して、友人の医者に整形外科医院と眼下医院を開業してもらった。そうなると医薬分業だから自分の店にも利益がでるようになった。
そして、そのもうひとつあいていた空き店舗にはその両隣の医院の待合室ということでスペースを設けて、患者や住民たちの交流の場をもうけた。こうすることによりコンセプトを持った商店街づくりができるようになっていった。
きっとコンセプトのある商店街づくりとはこういうことなのだろうと思う。
・できないことは人にやってもらう
人にはやれることとやれないことがある。だからこそ、それぞれの得意分野をうまく融合させることが大事で、さきほどの自分の薬局と両隣の医院の関係にも似ている。何でもすべて自分がマルチになってやる必要はないわけで、自分ができないところは、できる人にやってもらい、それぞれが役割分担しつつ、また切磋琢磨しながら高めあう、そういうようなグループをつくることが大事である。
宮明さんに貴重なお話をうかがったのちは、物産所に立ち寄ってお土産を購入するなどして、佐伯市の古い町並みを市の観光ボランティアガイドの方によりウォッチングしました。
トンカツならぬ「ブリカツ」です。ブリカツ丼なるものもありました。
ボランティアガイドさん。もとはバスガイドさんということで、流暢なガイドにみなさん聞き惚れておりました。ガイドの途中の雑談にでてくる佐伯の方言が素朴でとっても素敵でした。
ガイドの様子
佐伯市も古い街並みが残っています。
マンホールには国木田独歩の詩が。
佐伯市と言えば、なんといっても国木田独歩です。どんな人だったかは知らない人は調べてくださいね。
ちょうど、塀を修復している工事現場を見ることができました。
お家のところどころに飾り瓦があり、ウォッチングにもたまらないところです。
ところどころかわったおうちもあります。
途中で抹茶の休憩なども少々・・・。
ガイドさんと一緒に佐伯のおいしいお食事と美しい風景を堪能いたしました。また、成人式の新成人に古い街並みで写真撮影をするといった仕掛けや、ミニ四国八十八か所を発掘しようとするなど、ガイドさんの地域づくりにかける熱い思いも聴かせていただきました。
愛媛から海をへだてたところにある大分県。特に佐伯市や臼杵市などはあまり行く機会がないところではありますが、ふたつの市のまちづくりから学ぶことが多かった研修だったように思います。
(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)



