- 地域の可能性を見つけるために -
先進地等への派遣支援
元気な集落づくり応援団「関係人口」創出事業
愛媛県から委託を受け、地域活動の人手が不足している集落と元気な集落づくり応援団(ボランティアで集落を応援したい団体)双方のマッチングを行っています。ボランティア活動を推進することで関係人口を創出し、集落の維持を図っています。
※申請書はメール等の利用による提出も受け付けています。
センター メールアドレス:ehime-chiiki@ecpr.or.jp
令和6年 6月 1日(土) 松山市久谷地区 第3回松山くぼの町ホタル祭り
令和5年 6月 3日(土) 松山市久谷地区 第2回松山くぼの町ホタル祭り
令和5年 7月 9日(日)久万高原町中津地区 旧中津小学校清掃活動
令和5年10月15日(日)伊予市大久保集落 中間道、排水溝の清掃活動
令和5年11月12日(日)伊予市佐礼谷地区 されだにきてみんさい
令和6年 2月18日(日)伊予市大久保集落 桜の植樹、地域交流会
令和6年 3月31日(日)久万高原町中津地区 中津さくらまつり
- 地域運営を高次化する -
地域×専門家マッチング支援
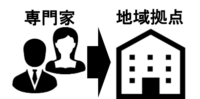
地域の課題解決に適した専門家と地域をマッチングし、専門家派遣に係る費用をセンターが支援します。
対象:法人化や組織運営に課題を抱える地域運営組織
地域運営組織化を検討している集落 など
ご希望の方は申込用紙に必要事項を記載し、当センターへご提出ください。
申込期限:令和6年6月17日(月)
移住交流促進事業
移住促進や交流人口拡大を図るため、移住フェアの開催や、「愛媛ふるさと暮らし応援センター」の運営を行っております。地方においては人口減少や少子高齢化の深刻化が課題となっており、持続可能な地域社会の構築のためにも移住・定住促進の重要性が高まっています。
また、(一社)えひめ暮らしネットワークと連携しながら、セミナー等の開催を通じて愛媛県の魅力や移住促進へ効果的な情報を発信しています。
移住に関する情報はこちら!
【愛媛県公式】移住ポータルサイト | えひめ移住ネット https://e-iju.net
大学生と県内企業によるアイデア会議開催事業
令和4年度 大学生と県内企業によるアイデア会議開催事業を実施いたしました。
御協力いただいた企業、参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。
詳細は(【開催結果】令和4年度 大学生と県内企業によるアイデア会議)をご覧ください。
事業は年2~3回を予定しています。
大学生と企業の若手経営者等の地域人材が協働し、地域資源を活用した商品企画等を行うアイデア会議を実施します。単なる情報としてではなく、学生自身の体験を通じて「地域の魅力」「地域の仕事」「地域で活躍する人材」を知る機会を創出します。
地域づくり活動アシスト事業(旧「まちづくり活動アシスト事業」)
令和6年度地域づくり活動アシスト事業の助成団体募集は終了しました。
詳細は、こちらのページをご覧ください。
地域を活性化するために活動している県内の地域づくりグループ(自治体・民間・学生による組織等)に対して、活動費の一部を助成する『地域活動アシスト事業』を行っています。 目的は、地域における地域づくり活動の活性化、活動事例を発表する機会を通じて他団体とのネットワークづくりの促進等です。
毎年6団体ほどの地域づくりグループに助成を行っています。
詳細は、次の過年度実施状況をご参照ください。
まちづくり活動アシスト事業過年度実績(令和元年度~令和4年度)
愛媛地域づくりアワード・ユース
次世代の地域づくりの担い手となる高校生を対象に、地域づくりに関する実践活動の発表及び表彰を行う愛媛地域づくりアワード・ユースを開催しています。
アワード・ユースは、地域活性化を目的として平成29年度から実施しており、愛媛県下全85校(県立・私立・高専を含む)から地域づくりに関する実践活動を募集しています。














